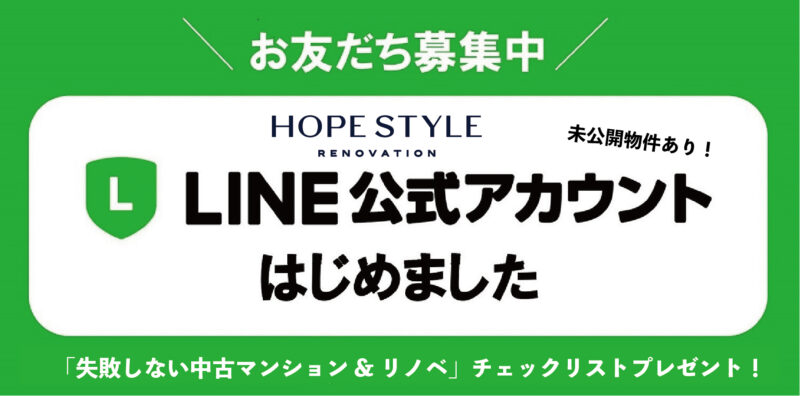中古マンションを購入する際、多くの人が気になるのが「不動産取得税はいくらかかるのか?」という点です。
実は、一定の条件を満たせば「不動産取得税がかからない」こともあります。
この記事では、中古マンション購入時に不動産取得税がかからない条件や軽減措置の詳細、注意すべき手続き、そして計算方法まで、専門的かつ分かりやすく解説します。これから中古マンションの購入を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
目次
中古マンションに適用される不動産取得税の軽減措置
中古マンションを購入する際、不動産取得税という名の出費が頭をよぎる方は多いでしょう。
高額な税負担に対して不安を感じる人も少なくありませんが、実は不動産取得税には大きな「軽減措置」が用意されています。
特に居住用住宅に関しては、一定の条件を満たすことで課税額が大幅に軽減されるか、場合によっては0円になる可能性すらあります。
軽減措置の基本条件とその内容を詳しく解説
不動産取得税の軽減措置は、特に「自己居住用の住宅」を購入する場合に強力な効果を発揮します。制度の趣旨としては、住宅取得にかかる負担を軽くし、居住環境の整備を支援するという目的があるため、居住用であることが最大のポイントになります。
軽減措置の主な条件は以下の通りです。
- 自分自身または家族が実際に居住する目的で取得する住宅であること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること(登記面積で判断)
- 築年数が一定以内であること(木造は築20年以内、耐火建築物は築25年以内)
このような条件を満たしている場合、建物に対して1,200万円までの控除が適用されます。たとえば、固定資産評価額が1,000万円の建物を取得した場合、1,200万円の控除によって不動産取得税の課税対象額がゼロとなり、結果として税額は0円になります。
また、建物だけでなく、土地にも軽減措置が用意されています。
土地に関しては、一定の計算式に基づいて税額が減額される仕組みで、土地の評価額が高い場合でも税負担が抑えられるようになっています。具体的な計算には「住宅1戸あたりの敷地面積の2分の1に対して、1㎡あたり10万円を控除する」といったルールが存在します。
これらの軽減措置を適用するには、取得後に都道府県へ申請する必要があります。申請を怠ると自動的に軽減されることはないため、どれだけ条件を満たしていても本来の税額が請求されてしまいます。
築年数による控除額の違いに注意
軽減措置のなかで、最も注意すべきポイントの一つが「築年数の条件」です。
中古マンションの購入者にとって、この要件が軽減措置の適用可否を左右する重要な分岐点となります。築年数の制限により、同じ価格帯の物件でも、軽減の対象になるかどうかが大きく変わってくるからです。
基本的に、木造住宅は築20年以内、耐火構造(鉄筋コンクリート造など)は築25年以内であることが、軽減措置の前提条件です。これは、築年数が古くなるほど建物の資産価値が減少するという考え方に基づいており、古すぎる物件に対しては税の優遇を受けられない可能性が高くなるということを意味します。
たとえば、築30年の木造中古マンションを購入した場合、原則として軽減措置の対象にはなりません。しかし、この条件には例外があります。
建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する「耐震基準適合証明書」を取得すれば、築年数の制限を超えていても軽減措置を適用できる場合があるのです。
この証明書は、専門の建築士などによる調査を通じて発行されるもので、発行には数万円の費用がかかることもありますが、それによって数十万円の不動産取得税が軽減またはゼロになる可能性を考えると、十分に元が取れるケースがほとんどです。
また、築年数によって固定資産評価額も変動するため、評価額自体が下がっている物件では控除額とのバランスが変わってきます。築年数が経過していても評価額が低ければ、控除額が評価額を上回り、結果として税額がゼロになるケースもあるため、単に築年数だけで判断するのは早計です。
不動産取得税がかからないケースとは?
中古マンションを購入した際、多くの方が当然のように「不動産取得税は支払わなければならないもの」と思い込んでいます。しかし、実際にはこの税金が「かからないケース」が存在します。
無駄な支出を防ぐためにも、「不動産取得税がかからない」ケースについて正確に把握しておくことが大切です。
築20年以内などの条件で非課税になる場合も
不動産取得税がかからない最大のポイントは、「課税標準額が軽減控除を下回る」状態になることです。つまり、固定資産評価額から控除額を差し引いた結果、残額がゼロまたはマイナスになれば、税額は0円となります。
具体的な例を挙げると、以下のようなケースが該当します。
たとえば、築15年の鉄筋コンクリート造の中古マンション(耐火構造)を購入したとします。
この物件の固定資産評価額が800万円だった場合、1,200万円の建物軽減控除がそのまま適用されると、評価額から控除額を引いた課税標準額はマイナス400万円になります。この場合、課税対象が存在しないため、不動産取得税はかかりません。
さらに、土地についても一定の軽減措置が適用されることで、土地部分の不動産取得税もゼロになることが多く、結果として「建物+土地=不動産取得税0円」という状況が生まれます。これは決して特殊な例ではなく、築浅で一定の条件を満たす中古マンションではよく見られるパターンです。
加えて、住宅ローン減税と同様に、自治体によってはさらに独自の軽減措置を設けていることもあります。
しかし注意すべきなのは、「かからない=申請不要」ではないということです。不動産取得税がゼロになるかどうかは、控除申請を行った上で初めて判断されます。つまり、条件を満たしていても申請を怠れば、軽減は適用されず、本来かからなかった税金を支払うことになりかねません。
軽減措置の対象になるために必要な手続きとは
中古マンションの不動産取得税における軽減措置は、条件さえ満たしていれば誰でも適用を受けられる非常に有利な制度です。
しかし、その恩恵を確実に受けるためには、「必要な手続きを適切に行うこと」が絶対条件となります。
せっかく築年数や床面積などの条件をクリアしていても、所定の申請を怠ってしまうと、軽減措置は適用されず、思いがけない出費が発生してしまいます。
申請書類と提出期限を把握しよう
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、各都道府県が定める「軽減申請書」とともに、所定の添付書類を提出する必要があります。
これらの書類は、税務署ではなく「不動産取得税を管轄する都道府県税事務所」に提出します。申請には期限が設けられており、一般的には「納税通知書が届いてからおおむね60日以内」とされていますが、自治体によって若干の違いがあるため、個別に確認することが重要です。
具体的な提出書類としては、以下のようなものが求められます。
- 軽減申請書(都道府県の様式に基づく)
- 売買契約書のコピー
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 建築年月日がわかる書類(登記簿や検査済証など)
- 建物図面・公図
- 固定資産評価証明書
- 耐震基準適合証明書(築年数が超過している場合)
これらの書類を揃えるには時間がかかることもあり、特に耐震基準適合証明書は専門家の調査が必要となるため、取得までに数日から数週間を要するケースもあります。
実際、申請を後回しにしてしまい、提出期限を過ぎてしまったことで、数十万円の税金を支払わざるを得なかったというケースは少なくありません。
特に、納税通知書が届いて初めて不動産取得税の存在を知った場合、申請期限との猶予が短く、慌てて準備しても間に合わないことがあります。
こうしたトラブルを避けるためには、購入後すぐに都道府県税事務所に連絡し、自分が該当するかどうかを確認したうえで、必要書類を正しく準備することが不可欠です。
ホープスタイルでは、世に出回っていな「未公開物件」をHP上だけで皆様にお届けしています。
大阪府の物件を見てもらい、自分たちにあった建物を知ることから、スタートしてみるのも一つではないでしょうか。ぜひ一度、
以下のリンクから物件情報をご覧ください。
不動産取得税の税額はこう計算する
不動産取得税は事前にある程度の金額を試算できる税金であり、その仕組みを理解しておけば、購入時の予算設計や資金計画に大きく役立ちます。
納付時のショックを回避するためにも、税額の計算方法についてしっかりと理解しておくことが大切です。
計算に必要な情報と計算方法を実例で紹介
不動産取得税は、「固定資産評価額」に対して一定の税率を掛けることで算出されます。ただし、評価額そのままに課税されるのではなく、条件に応じてさまざまな控除が適用されるため、「課税標準額」を正確に把握すること」が計算の出発点となります。
計算に必要な主な情報は次の通りです。
- 建物の固定資産評価額(市区町村で発行される評価証明書から確認)
- 土地の固定資産評価額
- 築年数、建物構造(軽減措置の適用判断に必要)
- 取得目的(居住用か投資用か)
- 床面積(50㎡以上240㎡以下であること)
不動産取得税の計算式は、以下のようになります。
(固定資産評価額 - 各種控除額) × 税率(3%または4%)= 不動産取得税額
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 中古マンション(RC造、築15年)を自己居住用に購入
- 建物の固定資産評価額:1,000万円
- 建物に適用される軽減控除:1,200万円
この場合、控除額の方が評価額を上回っているため、課税標準額はマイナス200万円となります。実際の計算では、課税標準額がゼロとみなされるため、建物部分の不動産取得税は0円です。
さらに、土地部分にも軽減措置があり、土地の評価額が800万円だった場合でも、一定の計算式に基づいて数十万円単位の控除が適用されるため、結果的に土地の不動産取得税も0円、あるいはごくわずかな税額で済むことがあります。
税率についても確認しておきましょう。住宅用建物の場合、原則は3%、非住宅用やその他の取得には4%が適用されます。
このように、税額の算出には複数の要素が関わるものの、ポイントを押さえておけば事前の試算は十分に可能です。
事前に把握していなかったばかりに、後から数十万円の出費が発生するというような事態を避けるためにも、正しい計算方法を知っておくことが重要です。

中古マンションの価格別に見る不動産取得税の目安
中古マンションを購入する際に、気になる「不動産取得税」ですが「おおよその税額目安」を把握しておけば、資金計画を立てるうえで大きな安心材料になります。
特に軽減措置の有無によって税額は大きく変動するため、物件価格帯ごとにどのような差が生まれるのかを理解しておくことが非常に重要です。
価格帯ごとのシミュレーションで理解を深める
中古マンションの価格に応じた不動産取得税の目安は、単純な計算では済まされません。なぜなら、実際に税額が計算されるのは「売買価格」ではなく、「固定資産評価額」に基づいているからです。固定資産評価額は一般的に売買価格の6〜7割程度で設定されることが多く、築年数や立地条件などによっても大きく左右されます。
たとえば、3,000万円で購入した中古マンションの建物部分の固定資産評価額が2,000万円だった場合、そこから軽減措置により1,200万円の控除が適用されると、課税標準額は800万円となります。
この800万円に税率3%をかけると、建物にかかる不動産取得税は24万円となります。しかし、これはあくまで軽減措置を受けた後の話です。軽減措置がなければ、税率が異なったり、控除額が減少したりするため、税額はさらに高額になる可能性があります。
以下は、物件価格別に想定される不動産取得税の「目安」と「軽減後の想定税額」の一例です。
- 物件価格:1,000万円
評価額:約700万円、控除額:1,200万円 → 税額:0円 - 物件価格:2,000万円
評価額:約1,400万円、控除額:1,200万円 → 税額:約6万円 - 物件価格:3,000万円
評価額:約2,100万円、控除額:1,200万円 → 税額:約27万円 - 物件価格:4,000万円
評価額:約2,800万円、控除額:1,200万円 → 税額:約48万円
このように、評価額が控除額を下回っているかどうかが「税額ゼロか否か」の分岐点となります。
特に1,000万円台の物件では、評価額が700万円以下に収まることも多く、軽減措置によって税額がゼロになる可能性が高くなります。一方、3,000万円を超える物件になると、評価額も高くなりがちで、控除額では補いきれない部分が出てきます。そのため、税額も相応に発生するケースが増えてくるのです。
注意すべき点として、軽減措置は「建物」に対するものであり、「土地」については別の計算式に基づいて軽減措置が行われます。土地部分の税額は、建物に比べると比較的少額になる傾向にありますが、物件によっては数万円程度の課税が生じることもあります。
正確な情報をもとに試算を行い、税金を含めたトータルコストで中古マンションの購入を判断することが、後悔のない選択につながります。
ホープスタイルは、皆様のご予算に合わせた「物件」と「リノベーションプラン」をご提案しています。
その際に必要になるのが、予算のシミュレーションです。
おおよその予算シミュレーションをしておくだけでも、イメージの湧き方が違いますので、ぜひ以下のリンクからお試しください。
軽減措置を受け忘れた場合の対応方法
中古マンションの購入において、不動産取得税の軽減措置は大きな節税効果を持ちます。「申請を忘れてしまった」「存在を知らなかった」といった理由で、本来払わなくてもよかった税金を支払ってしまうケースが少なくありません。
ここでは、申請忘れに対する具体的な対応方法について詳しく解説します。
申告漏れでも還付されるケースとは
不動産取得税の軽減措置は、都道府県税事務所に対して、所定の申請を行うことで初めて適用されます。
通常、申請期限は納税通知書の送付日からおおよそ60日以内とされていますが、この期限を過ぎてしまった場合、「もう軽減措置は受けられない」と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。実はそれは誤解です。申請忘れであっても、一定の期間内であれば還付申請という形で税金が戻ってくる場合があります。
たとえば、軽減措置の条件をすべて満たしていたにもかかわらず、申請を行わなかったために全額を納税してしまった場合、その後に必要書類を整えて還付申請を行うことで、納めた税金の一部または全額が戻る可能性があります。
還付申請を行うためには、以下のような書類を提出する必要があります。
- 還付申請書(自治体が用意した様式)
- 軽減措置対象であることを証明する書類(売買契約書、登記簿、建築確認書、耐震基準適合証明書など)
- 納税済証明書または納付書の控え
- 本人確認書類
- 還付金の振込先口座情報
申請期限は自治体によって異なるものの、多くの場合「納税した日から5年以内」が一つの目安とされています。ただし、時間が経過すればするほど手続きが煩雑になったり、書類の紛失リスクが高まったりするため、早めの対応が推奨されます。
とはいえ、そもそも軽減措置は「申請して初めて適用される制度」です。
仮に申請を忘れてしまったとしても、冷静に対応し、速やかに還付の手続きを取ることで、経済的な損失を最小限に抑えることができます。
固定資産評価証明書を使って税額の目安を確認
不動産取得税を正確に見積もるためには、「固定資産評価証明書」が欠かせません。多くの方が中古マンションの購入にあたって「いくら税金がかかるのか分からない」と不安を抱えるのは、評価額と実際の税額が連動している仕組みを把握していないからです。
固定資産評価証明書とは何か、どこで取得できるのか
固定資産評価証明書は、市区町村の資産税課が発行する書類で、その不動産に対して自治体が評価した価値(評価額)が記載されています。これは毎年1月1日時点の評価に基づいており、不動産取得税の課税標準額として使われる重要なデータです。評価額は売買価格よりも低めに設定されることが多く、概ね6~7割程度が一般的な目安とされています。
証明書の取得方法は非常にシンプルです。購入を検討している物件がある場合、その所在地の役所(市区町村役場)の資産税担当窓口に申請すれば、1件あたり数百円程度の手数料で発行してもらえます。
事前に予約や本人確認書類の持参が必要な自治体もあるため、役所のホームページなどで詳細を確認しておくとスムーズです。また、代理人申請が可能な場合もありますので、不動産会社や司法書士などに依頼するケースも見受けられます。
この証明書を取得することで、建物や土地の固定資産評価額を知ることができ、それを基に不動産取得税の概算を事前に計算することが可能になります。
また、税額の見積もりだけでなく、軽減申請時にもこの評価証明書が必要書類として求められるため、早めに取得しておくことが望ましいです。
中古マンションを購入する際には、単に「いくら払えばよいか」ではなく、「なぜこの金額になるのか」を理解することが、賢く税金対策を進めるための鍵となります。
不動産取得税以外にかかる購入時の諸経費とは
中古マンションの購入を検討する際、さまざまな諸経費がかかります。「不動産取得税」は代表的な費用のひとつですが、それ以外にも見落とされがちなコストがいくつも存在します。
こうした諸経費を事前に把握しておくことで、資金計画に余裕を持たせ、後から慌てることなく安心して購入を進めることができます。
購入時に必要となる主な諸経費を一覧で理解しよう
中古マンション購入時には、不動産取得税以外にも次のような諸費用が発生します。
- 登記費用(登録免許税+司法書士報酬)
不動産を購入したら、法務局で所有権の移転登記を行う必要があります。この際に発生するのが登録免許税で、土地や建物の評価額に一定の税率をかけて計算されます。さらに、登記を代行する司法書士への報酬も必要になります。 - 仲介手数料
不動産会社を通じて物件を購入した場合、仲介手数料が発生します。これは物件価格の3%+6万円(消費税別)が一般的な相場です。たとえば2,000万円の物件なら、約72万6,000円(税込)程度になります。かなり高額になるため、あらかじめ予算に組み込んでおくことが大切です。
仲介手数料については以下の記事で詳細に解説していますので、ご覧ください。
関連記事:中古マンション仲介手数料の相場や無料にする方法まで徹底解説
- 住宅ローン関連費用
住宅ローンを利用する場合には、金融機関への保証料、事務手数料、団体信用生命保険料などの諸費用が発生します。これらも数十万円に及ぶことがあり、借入金額や銀行によって異なります。固定費として見逃せないコストの一つです。 - 火災保険料・地震保険料
住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入は必須条件です。また、地震が多い日本では、地震保険にも加入する人が多い傾向にあります。保険期間や補償内容によって費用は異なりますが、5年契約で10万円前後が一般的です。 - 管理費・修繕積立金の前払い
中古マンションでは、購入時に管理費や修繕積立金の前払いが求められることがあります。1ヶ月分〜3ヶ月分が目安とされており、物件によっては数万円〜十数万円をまとめて支払う必要があります。 - リフォーム費用(任意)
中古マンションをそのまま使うのではなく、内装を変更したいという場合には、別途リフォーム費用が発生します。キッチンや浴室の交換、クロスの張り替えなど、工事の内容に応じて数十万円から数百万円かかるケースもあります。
このように、中古マンションを購入する際には、物件価格のほかに合計で数十万〜100万円以上の諸経費が必要になるのが一般的です。中には住宅ローンに組み込める費用もありますが、すべてをローンに含められるわけではないため、現金で準備しておくべき金額も把握しておく必要があります。
中古マンションの不動産取得税に関するよくある質問
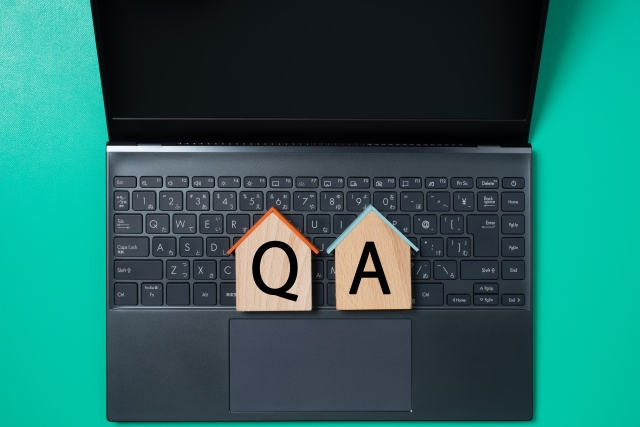
中古マンションを購入する際、多くの方が不安に感じるのが税金に関することです。なかでも不動産取得税は、「いつ、いくら払うのか」「本当に払わなければいけないのか」「手続きはどうすればよいのか」など、多くの疑問が寄せられます。
ここでは、購入検討者からよくある質問をピックアップし、具体的かつ分かりやすく解説していきます。
Q.「不動産取得税はいつ払う?」
不動産取得税の納付時期は、購入後すぐに発生するわけではありません。多くのケースでは、登記完了後からおよそ3~6ヶ月後に、都道府県税事務所から納税通知書が郵送されてきます。つまり、「突然届く税金」であることが多く、事前に準備していないと予期せぬ出費に戸惑うことになりかねません。
この納付書が届いてから、通常は1ヶ月程度の納付期限が設けられています。
コンビニ払いや銀行振込、口座振替など、支払い方法も複数選べるのが一般的です。
いずれにしても、突然の支払いに焦らないように、物件の購入時点から「不動産取得税は後から来る」ということを前提に、資金を確保しておくことが重要です。
Q.「不動産取得税がかからない場合があるって本当?」
はい、条件を満たせば不動産取得税がかからない場合は十分にあります。具体的には、建物の固定資産評価額が軽減措置による控除額を下回る場合、課税対象がなくなるため、税額が0円になります。
ただし、軽減措置は自動で適用されるわけではなく、あくまで申請が必要です。条件を満たしていても、申請しなければ通常通りの税額が課税されるため、注意が必要です。
Q.「不動産取得税の申告や軽減措置の手続き方法は?」
不動産取得税の軽減措置を受けるには、購入後に都道府県税事務所に対して申請を行う必要があります。提出書類は各自治体によって多少異なりますが、主に以下のものが求められます。
- 軽減申請書
- 売買契約書のコピー
- 登記事項証明書(登記簿)
- 固定資産評価証明書
- 建物の建築年月がわかる書類
- 耐震基準適合証明書(築年数オーバーの場合)
これらをそろえて、納税通知書が届く前に提出するのが理想的です。納税通知が届いた後でも、所定の期間内であれば還付申請によって軽減措置を受けることが可能なケースもあります。
Q.「中古マンションを購入する時、不動産取得税以外にかかる諸経費はどのくらい?」
中古マンションの購入では、不動産取得税以外にも数多くの諸経費が発生します。主なものには以下のようなものがあります。
- 登録免許税(登記時)
- 司法書士報酬(登記手続き代行)
- 仲介手数料(売買価格の約3%+6万円+消費税)
- 住宅ローン関連費(保証料、手数料、団信保険料など)
- 火災・地震保険料
- 管理費や修繕積立金の前払い分
- リフォーム費用(任意)
これらを合計すると、物件価格の5〜10%程度が目安となります。
事前にこれらを含めた総予算を組んでおくことで、後からの資金不足やローンの見直しといったトラブルを回避することができます。購入検討段階から、不動産取得税だけでなく総合的なコスト意識を持っておくことが大切です。
「ちょっとした相談だけど大丈夫かな..」
ホープスタイルは、そのような簡単な相談も受け付けております。以下のリンクからお問い合わせや、ご相談のご連絡をいただければと思います。