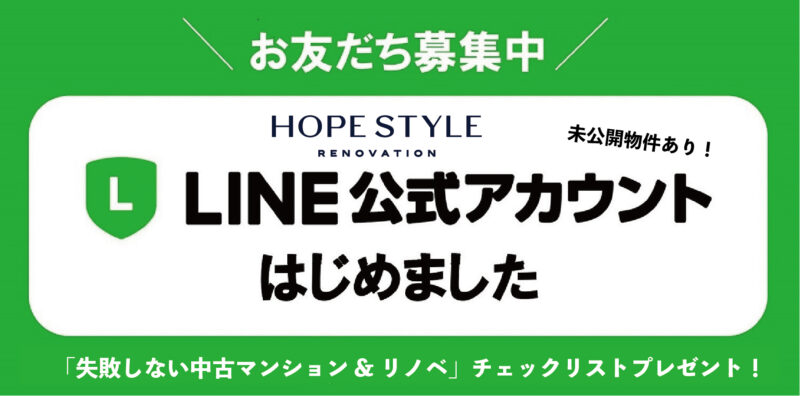中古マンションを売りたいのに、なかなか売れずに時間ばかりが過ぎてしまう。
価格を下げても、内覧者が来ても、まったく成約に至らない..そんな悩みを抱えている方は少なくありません。しかし、ただ待っているだけでは状況は好転しません。
この記事では、「中古マンションが売れない」と悩む方に向けて、原因の洗い出しから具体的な改善策、そして万が一売れないときの代替手段までを網羅的に解説します。
「どうして売れないのか?」「どうすれば売れるのか?」その疑問に、この記事が明確な答えを与えるはずです。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入や販売、リノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
目次
売却活動を始めたのに中古マンションがなかなか売れない理由とは
エリアの需要と物件特性がマッチしていない可能性がある
中古マンションの売却で最も重要なのは「立地」です。
どれだけ内装が美しく整えられていても、そもそもそのエリアに住みたいと思う人が少なければ、売却のチャンスは極端に限られてしまいます。
売却に悩んでいる方の中には「住んでいたときは便利だったし、環境も良い」と感じている方も多いでしょう。
確かに、売主にとっては生活しやすい環境だったかもしれません。しかし、現在の住宅購入者が重視するのは「将来性」「交通の利便性」「教育環境」「周辺のインフラ」など、購入後の資産価値も含めた観点です。
では、需要の少ないエリアにある物件は売れないのか? 答えはNOです。
そのような場合には、ターゲットを変えることが有効です。ファミリー層ではなく単身者、高齢者、セカンドハウス需要など、視点を変えることで売却の可能性は大きく広がります。
戦略を見直し、「どんな人ならこの物件を選ぶか?」を明確にした訴求を行うことで、問い合わせが増える可能性もあります。
売り出し価格が市場の相場とずれている
売れない最大の原因は「価格が高すぎる」ことです。売主としては少しでも高く売りたいと思うのは当然の心理ですが、買い手はシビアに比較検討しています。
同じエリアで同じ広さ、築年数の物件が1,980万円で売り出されているのに、自分の物件を2,380万円で出しても、問い合わせすら来ないのは当然です。
価格設定に自信がある方も、実は根拠が「近所で似たような物件がこのくらいだった」「不動産会社に言われた金額」程度だったりします。
ところが、不動産の価格は条件のちょっとした違い(角部屋かどうか、階数、方角、眺望、管理状態)で大きく変わります。つまり、適正価格を導き出すには「広範な市場調査」が不可欠なのです。
買い手側もポータルサイトで簡単に類似物件を比較できるため、「相場より高い」と判断された物件は最初から除外されてしまいます。逆に、適正価格に設定し直した途端に問い合わせが増えるというケースも実際に多くあります。
正しい価格設定をするためには、複数の不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。また、価格を「少しずつ段階的に下げていく」という戦略もあります。
これは「値下げしたことがバレたくない」という売主心理にも配慮しつつ、買い手の注目を集める効果があります。
築年数と劣化の状態が買い手の印象を左右している
中古マンションが売れない理由の一つに「築年数の古さ」がありますが、
それ以上に重要なのが「劣化状態」です。築20年を超えていても、きちんとメンテナンスされている物件は「まだまだ使える」と判断されます。一方で、築10年でも放置されていると「これから修繕費がかかる」として敬遠されるのです。
買い手は、購入後すぐに多額のリフォーム費用をかけたくありません。
そのため、壁紙の汚れ、フローリングの傷、浴室やキッチンのカビや劣化は、非常にマイナスの印象になります。
また、築年数に応じた「修繕履歴」があるかどうかもポイントです。マンション全体の大規模修繕がしっかり行われている場合は、管理状態が良好と判断されやすく、買い手の安心材料になります。逆に、長年修繕がされていないマンションは、資産価値が下がって見られます。
こうした点を踏まえ、「築年数が古いから売れない」と諦める前に、まずは自室の状態を見直すことが大切です。必要に応じて部分的なリフォームやハウスクリーニングを行い、「すぐに住める状態」に整えることで、築年数のマイナス要素を緩和できます。
中古マンションが売れない状態を放置するとどうなるか?
管理費・固定資産税などの維持費が積み重なる
中古マンションを売却しようとしてもなかなか買い手が現れず、そのまま放置している人は少なくありません。ですが、所有している以上は毎月・毎年確実に「コスト」が発生し続けます。
まず理解しておきたいのは、マンションは「住んでいなくてもお金がかかる資産」だということです。
代表的なのが「管理費」と「修繕積立金」。これらはマンションの共用部分の維持や将来的な修繕に備えるために徴収されるもので、たとえ空室であっても支払う義務があります。月に1万5,000円〜2万円が一般的で、これに加えて年に1回の固定資産税(地域や広さによって異なるが平均10万円前後)も発生します。
また、修繕積立金は築年数の経過とともに増額される傾向にあるため、「今は大したことがない」と思っても、5年後には1.5倍近くになることも珍しくありません。
このような維持費は、収益を生まない「死に金」です。しかも、相続が発生した場合、家族がこの負担を背負うことにもなります。売却が長引くことで生まれる金銭的損失は、精神的なストレスや家族関係のトラブルにもつながりかねません。
時間が経つごとに資産価値が下がるリスクがある
中古マンションは「時間との戦い」だと言っても過言ではありません。
築年数が1年増えるごとに、資産価値は確実に目減りしていきます。「まだ売らなくてもいいだろう」と思って放置していると、その間に価値が落ち続け、結果的に売却額が数百万円単位で下がることもあるのです。
日本の不動産市場において、築20年を超える物件の売却は一気に難易度が上がります。
これは単に「古くなったから」ではなく、「住宅ローンが組みにくくなる」「設備が時代遅れになる」「管理状況に疑念が生まれる」など複数の要素が重なるためです。
また、長期間売れずにポータルサイトに掲載され続けていると、買い手側に「売れ残り物件」と見なされ、敬遠される傾向も強くなります。売り出し初期の「新着物件」というアドバンテージを失ってしまうと、その後に価格を下げても関心が戻りづらくなるのです。
こうした状況を防ぐためには、「いま売れる価格で手放す」という判断が求められます。
売れない原因が「不動産会社」にある場合のチェックポイント
担当者が売却に消極的ではないかを確認する
中古マンションがなかなか売れないと感じているとき、意外な盲点となるのが「担当者の売却姿勢」です。
いくら良い立地や価格設定であっても、担当者の動きが鈍かったり、売却に対して消極的であれば、物件が埋もれてしまい、チャンスを逃す原因になります。
売主の多くは、「不動産会社に任せておけば安心」と思いがちです。
しかし実際には、担当者のスキルや姿勢によって売却活動の質は大きく左右されます。
こうした担当者の姿勢は、面談や日々のやり取りから見抜くことが可能です。
このような状況に直面したら、まずは担当者に具体的な活動内容と今後の販売戦略について質問してみましょう。それでも曖昧な回答しか得られない場合は、別の営業担当者に変更する、あるいは他社への切り替えを検討することが重要です。
媒介契約の種類を見直す必要があるかもしれない
不動産を売却する際には、「媒介契約」という契約形態を不動産会社と結ぶ必要があります。この契約の種類によって、売却活動の進め方や情報の露出範囲が大きく変わることをご存知でしょうか?
媒介契約には大きく分けて3種類あります。
1社とだけ契約し、他社には依頼できない「専属専任媒介契約」、1社のみに依頼するが売主が自力で買い手を見つけるのはOKな「専任媒介契約」、複数社に同時に依頼できる「一般媒介契約」です。
多くの売主は、不動産会社に強く勧められて「専任媒介契約」を選ぶ傾向があります。
もちろん専任契約には、不動産会社がより真剣に動いてくれる、定期報告義務があるといったメリットもありますが、反対に「その会社だけに売却活動を委ねる」というリスクも抱えることになります。
もし、現在の媒介契約先が十分に売却活動をしていない、広告の掲載範囲が狭い、積極性が感じられないといった状況であれば、「媒介契約の見直し」が必要です。
ただし、媒介契約を変更する際は注意も必要です。複数社が競合することで「囲い込み」や「価格競争による安売り合戦」が起きる可能性もあるため、信頼できる不動産会社に絞って依頼することが重要です。
内覧での第一印象がカギ!成約率を高める工夫とは
室内の整理整頓と清掃で印象アップを狙う
中古マンションの売却において、内覧時の第一印象は極めて重要です。買い手は写真や図面だけでは分からない「実際の住み心地」や「雰囲気」を重視しており、内覧の段階でその物件に対する購買意欲が大きく変動します。そこで鍵を握るのが、「室内の整理整頓と清掃」です。
売主の中には、「生活している状態のままで内覧を受けても問題ない」と考えている人もいます。しかし、それは大きな誤解です。買い手は物件そのものを見るだけでなく、「ここで自分が暮らすイメージ」を重ねながら見学しています。
まず着手すべきは、不要な家具や雑貨の撤去です。部屋を広く見せるためには、「空間の余白」がとても大切です。
続いて、徹底的な清掃が必須です。キッチン、浴室、トイレ、水回りは特に汚れが目立ちやすく、清潔感を重視する買い手にとっての評価ポイントとなります。カビや水垢、匂いなどがあると、たったそれだけでマイナス印象につながる可能性もあります。
さらに、玄関やベランダ、収納の中も抜かりなく整えておくことが重要です。意外とチェックされる部分であり、「大事に使われていた物件かどうか」を判断される材料にもなります。
もし可能であれば、プロのハウスクリーニングを依頼するのも効果的です。費用は数万円ほどかかりますが、その後の成約率や価格交渉の場面で「きれいな状態」が大きな武器になります。
短時間でアピールする内覧対応術を身につける
内覧の時間は、平均して30分〜1時間ほど。つまり、買い手の心を動かすには「限られた時間でどれだけ魅力を伝えられるか」が鍵になります。ここで必要なのは、「物件の魅力を的確に伝えるアピール力」と「買い手に安心感を与える対応力」です。
まず大前提として、内覧は「商品を売る営業活動」と同じです。
ただ見せるだけでなく、意識的に「ここがこの物件の強みです」「こんな生活ができます」といったポイントを押さえて案内する必要があります。担当の不動産会社が内覧対応をしてくれる場合もありますが、売主自身が在宅しているときには、一緒にポイントを伝えることで成約に近づくケースもあります。
さらに重要なのが、買い手に安心感を与える空気づくりです。内覧中に売主が過剰に話しかけたり、監視するように付き添っていると、かえって買い手が自由に見られず、萎縮してしまうことがあります。
逆に、ほどよい距離感を保ちながら、質問には丁寧に答える姿勢を見せることで、「この家の持ち主は信頼できる」と好印象を持たれることもあります。
加えて、事前に照明をすべて点けておく、空気を入れ替えておく、室温を快適に整えるといった基本的な準備も欠かせません。こうした細かな気遣いが、買い手の心を動かすきっかけになります。
それでも売れないときに検討すべき代替案
不動産会社による買取を依頼してみる
中古マンションがなかなか売れない。価格も見直し、写真も改善し、内覧対応も丁寧に行っているのに、それでも買い手がつかない。このような場合、売却方法そのものを変えるという選択肢があります。その中でも「不動産会社による直接買取」は、検討に値する現実的な手段です。
通常の売却は、一般の買い手を探して契約を結ぶ仲介型が一般的です。
しかし、仲介では時間がかかる、内覧対応が面倒、価格交渉が続くなど、売主にとって精神的・時間的負担がかかる場面が多々あります。一方、買取は、不動産会社が直接物件を買い取ってくれるため、スピーディーに現金化でき、煩雑なやりとりも最小限に抑えられます。
また、買取の場合はリフォームの必要がなく、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を免除できることも多いため、「トラブルを避けて早く手放したい」という方にも適しています。最近では、買取後にリフォームして再販する「リノベーション再販業者」が増えており、築年数の古いマンションでも買い取ってもらえるケースが広がっています。
ホープスタイルでは、中古マンションの購入からリノベーションまで一気通貫で行うことができる会社です。
大阪市で不動産物件の売却にお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。
賃貸として一時的に運用するという選択肢もある
「どうしても売れない」「でも安く手放すのは避けたい」という場合、売却ではなく“賃貸として運用する”という選択肢も有効です。
実際、賃貸に切り替えることで家賃収入を得ながら、数年後に市場が回復してから再び売却を検討するという流れは、不動産投資の一手法としても一般的です。
ただし、この選択には慎重な判断が必要です。賃貸物件として運用を始めた場合、入居者がいる間は原則として売却が困難になります。
借主の居住権が優先されるため、「すぐに売りたい」と思っても実行できない状態になります。また、入居者退去後の原状回復費用、空室リスク、管理会社への手数料など、収益が思ったほど残らないこともあるため、事前の収支シミュレーションは不可欠です。
さらに、家賃相場の把握も重要です。「売却すれば2,000万円になる物件」でも、「月7万円の家賃しか取れないエリア」であれば、長期運用による収益性は低くなる可能性があります。
賃貸への切り替えは、時間をかけて資産価値を維持したいと考える人にとって、一つの有力な手段です。ただし、単なる延命策ではなく、目的と将来の出口戦略を明確にしたうえで選ぶ必要があります。

中古マンションを売るために検討すべき「リフォーム」の判断基準
全面リフォームは必ずしも必要ではない
「マンションが売れないのは、古いからだろう」と思い込み、全面リフォームを検討する売主は少なくありません。しかし、実はこの判断は慎重になるべきです。なぜなら、リフォームにかけた費用が売却価格にそのまま反映されるとは限らないからです。
多くの人が、内装や水回りを一新すれば「高く・早く売れる」と信じがちです。
確かにリフォーム済みの物件は見た目がきれいで印象も良くなりますが、それだけで即売却につながるとは限りません。そうした買い手にとっては、売主の好みで仕上げられた全面リフォームはむしろマイナスになることもあります。
さらに、全面リフォームには数百万円単位の費用がかかるため、費用対効果の観点からも慎重な判断が必要です。
「高く売るためにリフォームする」というよりは、「本当にそのリフォームが売却に寄与するのか?」を冷静に見極めることが必要です。
リフォームの判断はエリアと市場の需要を基に行う
リフォームすべきかどうかの判断において最も重要なのは、「市場の需要」と「物件が属するエリアの特性」を正しく把握することです。
一地方都市や高齢化が進むエリアでは、リフォーム済み物件のニーズが必ずしも高くありません。
むしろ、「価格を抑えたい」「必要に応じてリフォームしたい」と考える買い手が多いため、高額なリフォームはかえって敬遠される可能性もあります。
また、不動産会社に相談すれば「このエリアではリフォーム物件が売れやすいか」「どの程度の改修が効果的か」といった情報も得られます。
リフォームの成否は、「自己判断」ではなく、「市場の目線」で考えるべきです。エリアの特性と買い手の傾向を読み解くことが、費用対効果の高い売却を実現するためのカギとなります。
まとめ
中古マンションが売れない。この悩みは決して珍しいものではありません。むしろ、現在の不動産市場では多くの売主が同じような壁に直面しています。しかし、焦りや不安から闇雲に行動するのではなく、「なぜ売れないのか」を冷静に分析し、それに見合った対策を講じることが、売却成功のカギとなります。
覚えてもらいたいのは、「売れない物件はない」ということ。どんな物件にも必ず適した買い手がいます。問題は、「その人に届いていない」「届く形になっていない」ことなのです。だからこそ、原因の洗い出しと対策の積み上げを冷静に行えば、必ず道は開けます。
中古マンションが売れないときこそ、売主としての真価が問われるときです。感情に流されず、戦略的に、かつ柔軟に対応することで、大切な資産を納得の形で手放すことができるでしょう。
「ちょっとした相談だけど大丈夫かな..」
ホープスタイルは、そのような簡単な相談も受け付けております。以下のリンクからお問い合わせや、ご相談のご連絡をいただければと思います。