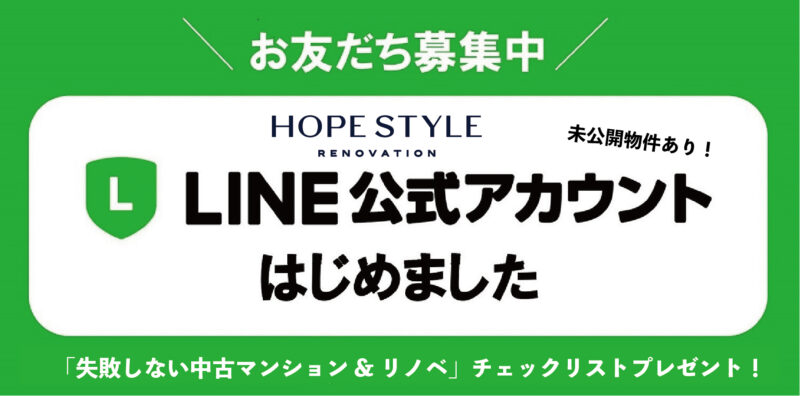中古マンションを購入して、自分好みにリノベーションする人が増えています。
新築よりもコストを抑えながら、理想の住まいを実現できるという自由度の高さが魅力ですが、実際にどれくらいの費用がかかるのか、どこまで自由に変更できるのか、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「中古マンション リノベーション 費用」に関するあらゆる情報を、初心者にも分かりやすく、かつ専門的に解説します。
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
目次
中古マンションをリノベーションする魅力とは?
中古マンションを購入して、自分好みにリノベーションするというライフスタイルが年々注目を集めています。
新築に比べて物件価格が抑えられることはもちろん、自由度の高い空間づくりが可能になるため、「コストを抑えながら理想の住まいを手に入れたい」と考える多くの人に選ばれています。
しかし、実際の魅力はそれだけではありません。暮らしに対する価値観やこだわりに合った家づくりができることが、中古マンション×リノベーションの最大の強みといえるでしょう。
リノベーションの大きな魅力の一つは、「既存の建物を活かしつつ、新しい価値を加えることができる点」にあります。
もう一つ見逃せないポイントが、「自由な設計が可能になる」ことです。
新築の建売住宅では、間取りや設備がすでに決まっているケースが多く、自分の理想をそのまま反映させるのは難しいのが現実です。一方、中古マンションのリノベーションでは、スケルトン状態からの設計が可能な場合もあり、「広いリビングにしたい」「家族の成長に合わせて間取りを可変にしたい」といった個別の希望を反映しやすいという特徴があります。
ただし、魅力ばかりに目を向けすぎると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも。中古マンションの中には、建物の構造上リノベーションの自由度が低い物件も存在します。
また、マンション全体の管理状態が悪かったり、修繕積立金が不足していたりする場合、将来的な負担が増える可能性もあるため、購入前には建物調査や管理状況のチェックが欠かせません。
中古マンションの購入で、後悔しないためのポイントについては、以下の記事でまとめております。
関連記事:中古マンションの購入で後悔しないためには?知っておくべき中古マンションのデメリット
購入費用を抑えながら理想の住まいを手に入れられる
新築マンションと比べて中古マンションは、立地や広さが同条件でも価格が2〜4割程度安くなる傾向にあります。
そのため、限られた予算の中でも立地条件を妥協せずに物件を選べるという大きな利点があります。浮いた予算をリノベーションに回せば、設備のグレードアップや間取りの変更など、より理想に近い住空間の実現が可能となります。
もちろん、安ければ良いというわけではなく、「コストに見合った価値をどれだけ得られるか」が重要です。建物の状態や周辺環境をしっかり見極め、信頼できる業者とパートナーシップを築くことで、安心して理想の住まいづくりを進めることができます。
間取り変更はどこまで可能?
間取り変更は、リノベーションの醍醐味とも言えるポイントですが、すべてのマンションで自由に行えるわけではありません。
構造的な制限や管理規約などのルールも存在するため、リノベーション計画の前に「できること」と「できないこと」をしっかりと把握する必要があります。
リノベーションでできること
まず、リノベーションで変更可能な代表的な内容としては、部屋の仕切りの撤去や移動、キッチンや浴室の位置変更、収納スペースの追加などが挙げられます。
例えば、和室を洋室に変更したり、独立型キッチンをオープンキッチンにするなど、日常生活の動線や視覚的な開放感を改善する工事は比較的よく行われています。これらは「専有部分」の中での変更であり、マンションの構造に直接関わらない範囲であれば、比較的自由に行えるケースが多いです。
リノベーションでできないこと
一方で、「どんなリノベーションも自由にできる」と誤解してしまうと、後で大きなトラブルにつながる可能性もあります。マンションは共同住宅である以上、建物全体の構造やルールに影響を及ぼす工事には厳しい制限がかかります。
特に、「共用部分」に関する変更は原則不可とされており、これはベランダ(バルコニー)や玄関扉、外壁などが該当します。また、構造体に影響を及ぼす梁・柱・耐力壁などは、撤去や移動ができないケースが多く、これによって希望する間取りが実現できないこともあります。
間取り変更を考える際には、建物の構造形式にも注意が必要です。マンションの構造には主に「ラーメン構造」と「壁式構造」の2つがあり、前者は柱と梁で構成されているため、間仕切り壁の撤去がしやすく、間取り変更の自由度が高いのが特徴です。
一方、壁式構造は壁そのものが建物を支えているため、撤去できる壁が限られており、設計の自由度が低くなります。購入予定の物件がどちらの構造かによって、リノベーションの可能性が大きく変わってくる点は見落とさないようにしましょう。
専有部分でも制限があるケースと注意点
専有部分とは、自分の所有する住戸の内部のことを指し、基本的には自由にリノベーションができる範囲とされています。しかし、実際には専有部分であっても、いくつかの重要な制限が存在します。その代表例が、構造体に関する部分や配管・配線などのインフラに関わる工事です。
さらに、マンションの管理規約や細則には、「施工可能な時間帯」「使用できる材料」「事前申請の義務」など、リノベーションに関する細かいルールが定められていることがほとんどです。そのため、リノベーションを検討する際は、まず管理規約を読み込み、必要に応じて管理会社や管理組合に確認を取ることが重要です。
中古マンションを購入して「自由に設計できる」と思っていたら、実は意外と制限が多かった、というケースは少なくありません。
リノベーション費用が変動する主な要因とは?
リノベーション費用が変動する主な要因として、まず挙げられるのが「工事の範囲と内容」です。しかし、間取り変更や水回りの移動、スケルトンリノベーション(骨組み状態まで解体して全面的に改装)など、工事の内容が高度で広範囲になるほど、費用は大きく膨らみます。
これは単に材料費が増えるだけでなく、施工にかかる人件費や工程数が増えることも関係しています。
次に、使用する設備機器や素材のグレードも費用に大きく影響します。また、壁や床材に天然素材を使うか、安価な建材を使うかでも費用は大きく異なります。予算を重視するなら「どこにお金をかけて、どこを抑えるか」のバランスをしっかり考える必要があります。
さらに、物件の築年数や構造、立地条件も見逃せない要因です。築年数が古い物件の場合、配管の劣化や構造の補強が必要となることが多く、想定外の費用がかかるケースがあります。また、エレベーターのない建物の高層階や、作業スペースの確保が難しい立地では、搬入や作業に手間がかかるため、工事費が割高になることもあります。
リノベーション費用を見積もる際には、これらの要因をすべて加味して、現実的な計画を立てることが重要です。
見積もり段階で希望を詰め込みすぎてしまうと、最終的に予算オーバーで工事内容を大幅に見直す必要が出てくることもあります。そうならないためにも、希望条件に優先順位をつけ、「ここは譲れない」「ここはコストを抑えたい」という線引きを事前にしておくことが、満足度の高いリノベーションにつながります。
工事内容や素材選びで費用は大きく変動する
リノベーションにかかる費用は、どのような工事を行うか、そしてどのような素材を使うかによって大きく左右されます。これは、解体、配管・配線のやり直し、断熱材の施工、間取り変更、内装仕上げなど、多くの工程が必要になるためです。
また、素材の選択も重要です。例えば、フローリング一つでも、合板フローリングを選ぶのか、無垢材を使うのかで、1㎡あたり数千円〜数万円の差が出ます。壁材や塗装、タイル、建具、キッチンカウンターなど、あらゆる箇所でこのような選択の連続があるため、トータルで見ると大きな金額差となって現れます。
設備機器に関しても同様です。ユニットバス、トイレ、洗面台、キッチンなどは、選ぶグレードによって価格差が数十万円になることもあります。デザイン性やブランド、機能性を重視する場合は当然コストが上がるため、何にどれだけこだわるかを明確にしておくことが、費用のコントロールに繋がります。
さらに、オーダー品か既製品かの違いも大きく影響します。造作収納やオリジナルキッチンなど、完全オーダーメイドにする場合は、設計費や施工費が別途必要となるため、総額が跳ね上がることがあります。理想の空間を追求するあまり、想定以上の出費にならないよう注意が必要です。
つまり、工事内容と素材選びは、費用に直結する最も重要な要素です。
平米単価で考えるリノベーション費用の相場感
リノベーションを検討するうえで、費用の目安としてよく使われるのが「平米単価」です。
これは1平方メートルあたりにかかるリノベーション費用のことで、工事全体のおおよその金額感を掴むために非常に便利な指標です。ただし、単価だけを見てリノベーション費用を判断するのは危険です。
一般的な中古マンションのフルリノベーションにおける平米単価は、15万円〜25万円程度が目安とされています。ただし、これはあくまで「標準的な仕様」での目安であり、デザイン性を高めたり、設備グレードを上げたりすれば、1㎡あたり30万円以上かかるケースも少なくありません。
平米単価が上がる主な要因としては、オーダーメイド設計、自然素材の採用、間取りの大幅変更、スケルトン工事の有無などが挙げられます。また、築年数が古い物件の場合、給排水管や電気配線の交換、断熱材の補強などが必要になることも多く、それに伴って費用が上昇します。一方で、表層リノベーションや部分的な工事に留めれば、10万円前後の平米単価で収まることもあります。
平米単価という考え方には「全体感を把握しやすい」というメリットがありますが、反面、「実際の内容を反映しきれない」というデメリットもあります。
つまり、数字だけを見て判断するのではなく、「この単価で何が含まれているのか?」をしっかり確認することが重要です。見積書を細かく見て、仕様や工事範囲、使用する材料などの内容まで精査しなければ、後から「思っていたより高かった」「必要な工事が含まれていなかった」という事態になりかねません。
リノベーション費用を検討する際には、「平米単価を起点に予算感をつかみ、詳細を詰めていく」という姿勢がとても有効です。
フルリノベーションと部分リノベーションの違いと費用例
中古マンションを購入した際、すべてを一新する「フルリノベーション」を選ぶか、必要な部分だけを更新する「部分リノベーション」にするかは、予算や目的によって大きく異なります。
それぞれの方法には明確な違いがあり、費用も大きく変動します。自分の理想とする暮らし方に合わせて、最適な選択をするためには、両者の特徴と相場感をしっかり理解しておくことが大切です。
まず、フルリノベーションは、既存の内装や設備をすべて撤去し、スケルトン(構造躯体)状態から空間を再構築する方法です。間取りの変更、配管や電気配線の交換、断熱工事、収納の再設計など、住まい全体を理想の仕様に作り直すことができます。自由度が非常に高く、まるで注文住宅のように一から自分仕様の空間を作り上げられる点が魅力です。
フルリノベーションの費用は、一般的に平米単価15万円〜25万円程度とされており、たとえば70㎡の物件であれば、約1,000万円〜1,750万円が相場です。ただし、デザイン性を重視したり、無垢材や高級設備を使ったりすると、30万円/㎡を超えることもあります。逆に、コスト重視で設備や仕様を標準的なグレードに抑えることで、費用を15万円/㎡以下に抑えることも可能です。
一方で、部分リノベーションは、既存の間取りや構造を活かしながら、必要な箇所だけを改修する方法です。たとえば、キッチンだけを入れ替える、浴室やトイレを新しくする、床や壁紙を張り替えるなど、ピンポイントでの改善が可能です。この方法のメリットは、費用が抑えられること、工期が短く済むこと、そして居住中でも施工が可能な点です。
部分リノベーションの費用は、工事内容によって大きく変わります。キッチンの交換であれば70万円〜150万円、浴室のユニットバス入れ替えで80万円〜130万円、トイレの交換で20万円〜40万円が相場となっています。床のフローリング張り替えは1㎡あたり1万円〜2万円程度、壁紙の貼り替えは1㎡あたり1,000円〜2,000円程度が目安です。
リノベーションを考える際には、「どこまで変えたいか」「どれくらいの予算があるか」「どんな暮らし方をしたいか」という点を明確にすることが重要です。すべてを理想通りにしたいならフルリノベーションが適していますが、予算を抑えつつ現状の課題だけを解決したい場合には、部分リノベーションが賢い選択となります。
理想と現実のバランスをとるには、専門家のアドバイスを受けながら、ライフプランに合ったリノベーションの形を見つけることが大切です。
ホープスタイルでは、世に出回っていな「未公開物件」をHP上だけで皆様にお届けしています。
大阪府の物件を見てもらい、自分たちにあった建物を知ることから、スタートしてみるのも一つではないでしょうか。ぜひ一度、
以下のリンクから物件情報をご覧ください。
費用を抑えたい人向け!コストを調整するための具体的な工夫
リノベーションは自由度の高い住まいを実現できる一方で、予算とのバランスを取ることが非常に重要です。理想を詰め込んだ結果、当初の想定より大幅に費用が膨らんでしまったというケースは決して珍しくありません。
しかし、工夫次第でコストを抑えながら満足度の高いリノベーションを行うことは可能です。ここでは、実際に取り入れやすいコスト調整の方法について具体的に紹介します。
まず、リノベーション費用を抑えるための第一歩は「優先順位を決めること」です。すべてにお金をかけていたら、どんなに予算があっても足りなくなってしまいます。「絶対にこだわりたい部分」と「妥協できる部分」を明確にし、予算配分にメリハリをつけることがカギとなります。
次に、素材や設備の選び方も費用に大きく影響します。すべてを高級素材で統一するのではなく、見える部分と見えない部分を使い分けることで、見た目の満足感を維持しつつコストを抑えることができます。
設備についても、型落ち商品やアウトレット品を上手く活用すれば、定価よりもかなり安く手に入れることができます。
さらに、DIYの活用も有効なコスト削減手段です。
壁紙の貼り替えやペンキ塗り、棚の取り付けなど、プロに頼まず自分でできる部分を見極めれば、工賃を大きく抑えることが可能です。もちろん、電気工事や水道工事のように専門的な知識が必要な部分は無理せずプロに任せるべきですが、「自分でできること」を見つけることで、予算の余裕を生み出すことができます。
また、リノベーション会社の選び方によっても、同じ内容でも費用に差が出ることがあります。
見積もりを取る際は、複数の会社に相見積もりを依頼し、価格だけでなく、工事内容やアフターサポート、担当者との相性なども含めて総合的に判断することが大切です。
なかには「定額制プラン」を用意している会社もあり、ある程度の仕様が決まっている代わりに、費用を明確に抑えられるというメリットがあります。
最後に、補助金や助成制度の活用も見逃せません。自治体によっては、省エネ改修や耐震補強などの工事に対して助成金が出るケースもあります。
ホープスタイルは「定額制プラン」をご用意しております。大阪で中古マンションを購入してのリノベーションをご検討中の方は、一度以下からお問合せください。
リノベーション費用の見積もりで失敗しないためのチェックポイント
リノベーションの計画が進んでくると、いよいよ「見積もり」という現実的な数字と向き合うステップに差しかかります。
この見積もりを甘く見てしまうと、あとになって予想外の出費が発生したり、当初のプラン通りに進められなかったりといったトラブルにつながります。理想を形にするリノベーションを成功させるには、見積もりの段階でしっかりと内容を把握し、納得のうえで契約を結ぶことが非常に重要です。
内容が明確か
まず確認すべきは、見積書に記載されている工事項目が「具体的であるかどうか」です。たとえば、「内装一式」「設備一式」といった曖昧な表記では、何にどれだけの費用がかかっているのかがわかりません。壁紙の張替え、床材の施工、キッチン設備の取り付けなど、それぞれの作業や材料が明確に記載されているかをチェックしましょう。曖昧な表現が多い見積書は、あとから追加費用が発生するリスクが高まります。
具体的か
次に注目すべきは、「設備機器や素材の仕様が具体的に示されているか」です。同じ「キッチン交換」と書かれていても、30万円台の製品から150万円以上の高級品まで幅があります。ブランド名や型番、仕上げ材の種類までしっかり書かれていれば、グレード感と金額の妥当性が判断できます。反対に、「標準仕様」や「同等品」といった表記だけでは、実際に何が取り付けられるか分からず、後のトラブルに繋がる恐れがあります。
総額が記載されているか
また、リノベーション費用には「直接工事費」だけでなく、「諸経費」や「設計費」「管理費」「解体・廃材処分費」なども含まれるのが一般的です。これらが別途計上されているか、それとも含まれているかを見落とさないことが大切です。一見すると安く見える見積もりも、必要な項目が抜けているだけの場合もあり、結果的に総額が高くなるケースも少なくありません。
工期
工期に関する記載も重要です。リノベーションの期間が不明確だと、住み始められる時期にずれが生じ、仮住まいや引っ越しの計画にも影響します。予定の工期、工事開始日、完成日などのスケジュールが記載されているか、工程ごとに確認しましょう。特に、マンションの場合は管理組合への申請や工事時間の制約もあるため、スケジュール管理は慎重に行う必要があります。
追加費用
そして忘れてはならないのが、「追加費用が発生する可能性の有無」です。
工事を進めていく中で、想定外の劣化や構造上の問題が見つかることは珍しくありません。その際に、どの範囲までが見積もりに含まれていて、何が別途費用になるのかを事前に確認しておくと安心です。「現場で状況に応じて判断」ではなく、あらかじめ追加発生のパターンと費用の目安を聞いておきましょう。
リノベーションの見積もりには専門的な用語や項目が並び、最初は戸惑うかもしれません。しかし、ここをしっかり理解しておかないと、理想の住まいづくりが「高くつく買い物」に変わってしまう危険性もあります。
不明点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。信頼できる業者であれば、きちんと応えてくれるはずです。
見積もりは「価格交渉のため」だけの資料ではありません。「理想の空間を、いかに無駄なく、トラブルなく実現できるか」を判断するための最も重要な指標です。
定額制リノベーションとは?メリット・デメリットを徹底解説
リノベーションを検討している人のなかには、「予算が心配」「費用がどんどん膨らむのが怖い」と感じている方も多いでしょう。
そんな悩みを抱える人にとって注目されているのが「定額制リノベーション」というサービスです。これは、あらかじめ施工範囲や設備・素材のグレードが決められており、提示された金額の中でリノベーションを実施できるというもの。見積もりのたびに費用が変わる不安がなく、コストコントロールがしやすい点が魅力です。
定額制リノベーションの最大のメリットは、「費用が明確で安心感がある」ことです。通常のリノベーションでは、プランの変更や工事中の追加対応によって、最初に提示された金額から大きくずれることがよくあります。
しかし定額制であれば、最初に決まった金額内でできることが明確になっており、追加費用のリスクを抑えることができます。住宅ローンや資金計画を立てやすくなるという点でも、安心材料になるでしょう。
また、定額制の多くは、プランや素材の選択肢が整理されているため、初めてリノベーションをする人でも「何をどう選べばいいかわからない」と悩みにくいという利点もあります。
あらかじめデザインテーマが決められていたり、内装・設備がバランスよく組み合わされたパッケージプランが用意されていたりするので、短期間で効率的にリノベーションを進めることが可能です。「おしゃれな家にしたいけどセンスに自信がない」という方にもおすすめです。
ホープスタイルは、皆様のご予算に合わせた「物件」と「定額リノベーションプラン」をご提案しています。
その際に必要になるのが、予算のシミュレーションです。
おおよその予算シミュレーションをしておくだけでも、イメージの湧き方が違いますので、ぜひ以下のリンクからお試しください。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。