
高齢化社会が進む中、多くの家庭で「将来の暮らしやすさ」を真剣に考える機会が増えています。特に、自宅で安心・安全に長く住み続けたいと望む方にとって、バリアフリーリフォームはその願いを実現する有効な手段の一つです。
転倒や事故を未然に防ぎ、自立した生活をサポートする住まい。それを実現するために、手すりの設置や段差の解消といった具体的な工事はもちろん、補助金・減税制度の活用方法まで知っておきたいところです。しかし、バリアフリーリフォームは一見シンプルに思えても、どこまで手を加えるべきか、どのように進めるべきか、判断が難しいケースも少なくありません。
そこで本記事では、「バリアフリーリフォームを検討するなら今知っておくべきポイントとは」というタイトルのもと、バリアフリーリフォームにまつわる疑問を徹底解説。
必要性のチェック方法から、リフォーム実例、費用の目安、制度活用法、注意点、成功のコツまで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
これからリフォームを考える方が、失敗せずに安心して進められるよう、網羅的なガイドとしてお届けします。
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
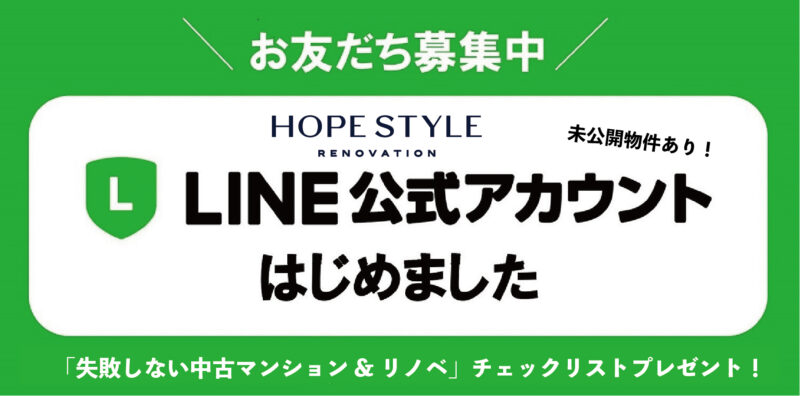
目次
バリアフリーリフォームの必要度をセルフチェック
誰にでも訪れる「年を重ねる」という人生の過程。その中で避けて通れないのが、体力や反応速度の低下、関節や筋力の衰えです。
今は元気な方でも、将来を見据えた住環境の整備は、決して早すぎることはありません。特に家庭内のちょっとした段差や滑りやすい床材が、思わぬ事故を引き起こす原因となり得るのです。
高齢者の住環境における事故は年々増加していますが、その多くは「予見可能」で「未然に防げる」ものばかりです。バリアフリーリフォームとは、そうした未来のリスクを減らすための「予防的リフォーム」と言えるでしょう。
とはいえ、いきなり工事を始めるのではなく、まずはご自身の住まいを冷静に見つめ直し、「どこにどのようなリスクがあるか」をチェックすることが大切です。
ここで紹介するセルフチェックは、バリアフリーリフォームの必要度を把握するための第一歩です。「うちはまだ大丈夫」と思っている方こそ、ぜひ一度ご確認ください。思わぬところに危険のサインが潜んでいるかもしれません。
我が家のバリアフリーチェック6項目
① 家の中に段差が多い
日常生活の中で無意識に越えている小さな段差。しかし、加齢により歩行バランスが崩れやすくなると、それが「転倒リスク」に直結します。特に廊下から部屋への境目や、トイレ・浴室の入口に多く見られるわずかな段差。これらが原因で転倒し、大腿骨骨折などの重篤なケガを招くケースも少なくありません。段差をフラットにするだけで、移動のしやすさと安全性が大きく向上します。
② 階段に手すりがない
階段の昇降は、身体機能の衰えを感じやすい動作の一つです。握力や脚力が低下すると、バランスを崩しやすくなり、階段の上り下りが非常に危険になります。手すりがあるだけで、体を支えながら安全に昇降できるようになります。片側だけでなく両側に手すりを設置することで、左右どちらの手でも体を支えられるようになり、より安心です。
③ 浴室やトイレに滑りやすい床材が使われている
浴室は住まいの中でも最も滑りやすく、転倒事故が起こりやすい場所です。特に濡れた床材は、若年層でも足を取られる危険性があります。加えて、トイレの床がタイルや光沢のある材質であれば、足元が不安定になる要因に。滑りにくい床材への張り替えや、防滑マットの活用など、小さな工夫で大きな安心を得ることができます。
④ 出入口のドアが引き戸でない
開き戸は、高齢者や車椅子利用者にとって扱いづらい構造です。特に身体のバランスが崩れやすい人にとって、開ける際の力や体のひねり動作は負担になります。引き戸であれば、少ない力で開閉できるうえ、開け放ったままにしておくことも容易で、通行性もアップします。プライバシーを確保しながら、使いやすさも両立できる優れた選択肢です。
⑤ 車椅子が通れる幅が確保されていない
今現在は歩行に支障がないとしても、将来的に車椅子や歩行補助器具を使う可能性があるなら、廊下やドアの幅は要チェックです。一般的な車椅子の幅は60cm前後。それに加えて旋回スペースを確保するためには、最低でも75〜80cm程度の通行幅が望ましいとされています。特に玄関やトイレなど、使用頻度の高い場所の幅はあらかじめ広げておくと、将来的な工事の手間も省けます。
⑥ 温度差が大きい場所がある
冬場の浴室や脱衣所、廊下などと居室との温度差は、ヒートショックによる健康リスクの大きな要因です。高齢者は温度変化に対する感知能力が低下しており、急激な温度変化が心筋梗塞や脳卒中を引き起こすことも。断熱材の導入や浴室暖房の設置によって、これらのリスクは大きく軽減可能です。安全な住まいづくりには、「温度環境」への配慮も欠かせません。
バリアフリーリフォームが大切な理由
誰しも年齢を重ねると、身体的な変化とともに生活スタイルにも配慮が求められます。特に自宅での生活環境が、そのまま事故やケガにつながる危険を含んでいることを見過ごしてはいけません。私たちが毎日何気なく過ごしている家の中には、実は多くのリスクが潜んでいるのです。
バリアフリーリフォームの本質は、単なる便利さの追求ではありません。最も大切なのは「事故やケガを未然に防ぎ、安心して生活できる空間を整える」ことです。とりわけ高齢者や身体に不自由のある方にとっては、住まいのちょっとした段差や使いづらさが命に関わる事態を引き起こすことさえあるのです。
この章では、なぜバリアフリーリフォームが必要不可欠なのか、その根拠を具体的なデータや事例とともに深掘りしていきます。
ケガの発生場所
ケガの発生は「外出先で起きるもの」と思っていませんか?実際には、日常の中で最も多くのケガが発生するのは「自宅」です。高齢者の転倒・転落事故の6〜7割以上が家庭内で起こっているという厚生労働省の統計もあります。これはつまり、最も安心すべきはずの「家」が、思わぬ危険に満ちているという事実を示しています。
特にリスクが高い場所として挙げられるのが「階段」「浴室」「トイレ」「玄関」です。いずれも毎日使用する場所であり、そこに存在する段差、濡れた床、狭い空間といった要因が、転倒や衝突の直接的な原因となっています。たとえば階段では、踏み外しやバランスの崩れが命に関わる大事故になることも。浴室では足元が濡れて滑りやすくなり、頭を打つケースが少なくありません。
また、高齢者の場合、一度の転倒が寝たきり状態に直結する可能性があります。骨折によって入院し、そのまま歩行能力が低下してしまうケースは、介護現場では決して珍しくないのです。
だからこそ、家庭内のケガの発生場所を事前に把握し、その原因をひとつずつ取り除いていくことが、バリアフリーリフォームの第一歩となります。安全で快適な暮らしを維持するには、「家の中で最も危険な場所はどこか?」を明確にし、対策を講じることが不可欠です。
家庭内でのケガの発生場所
住まいの中でもケガの発生率が高い具体的な場所について、さらに掘り下げてみましょう。
まず第一に多いのが「階段」です。段差の高さや踏面の幅が不均等だったり、手すりが片側だけ、もしくは全くなかったりすると、昇降時にバランスを崩して転倒しやすくなります。特に夜間の薄暗い時間帯には、足元が見えにくくなり、危険性が高まります。
次に「浴室」。ここは滑りやすい床、急激な温度変化、動作の不安定さという3つの要因が重なる非常にリスクの高い空間です。濡れたタイルの上で足を滑らせて転倒し、骨折や頭部外傷を負うケースも報告されています。バリアフリーリフォームでは、床材の見直しや、浴槽のまたぎ高さの低減、出入口を引き戸に変えるといった対策が効果的です。
「トイレ」も油断できません。スペースが狭く、身体の向きを変える動作が多いため、筋力の低下した高齢者には負担が大きい場所です。立ち上がり補助のための手すりや、便座の高さ調整などが必要とされます。
さらに「玄関」では、外履きと室内履きの履き替えの動作、段差の昇降がリスク要因となります。雨の日などは濡れた靴が滑ることもあり、ちょっとした油断が転倒につながるのです。ここでは段差解消のためのスロープ設置や、玄関のスペース拡張が有効です。
また、「廊下やリビング」などの比較的安全と思われがちな場所でも、コード類の放置やカーペットのめくれなどによる転倒事故が発生しています。家具の配置や照明計画、床材の素材に至るまで、見直すべき点は意外と多いものです。
これらの場所に共通するのは、「日常的に使う場所」であるという点です。使用頻度が高いからこそ、事故が起きた際の影響も大きく、繰り返しの使用によって予期せぬリスクが潜みやすくなります。
住み慣れた自宅だからこそ、気づきにくい「危険」があるという事実。バリアフリーリフォームは、それらを見つけ出し、確実に取り除いていくための手段です。事故が起きてから慌てて対処するのではなく、起きる前に備えることが、これからの住まいづくりのスタンダードになっていくべきです。
減税制度や補助金の活用で実質負担額を軽減
バリアフリーリフォームを検討している多くの方が、最も気にするのが「費用面」ではないでしょうか。住まい全体のリフォームとなれば、数十万円〜数百万円の費用がかかることも珍しくありません。
しかし、安心してください。国や自治体が提供する減税制度や補助金制度を上手に活用することで、実際の自己負担額を大きく抑えることが可能です。
ただし、制度には細かな条件が定められており、申請には期限や書類の提出が必要なケースがほとんどです。そのため、制度を知らずに手続きができなかったという声も多く聞かれます。
リフォーム計画を立てる段階から、こうした制度の利用を前提に考えておくことで、経済的な負担を軽くし、より安心してリフォームを進めることができます。
以下では、実際に活用できる主な減税・補助制度について、それぞれ詳しく解説していきます。
バリアフリーリフォームの減税制度
住宅におけるバリアフリー改修に対しては、一定の条件を満たすことで「所得税控除」や「固定資産税の軽減措置」といった減税が受けられます。
これらは、国が積極的に推進している高齢者支援政策の一環として整備された制度であり、申請すれば誰でも受けられるわけではありませんが、要件に該当すれば非常に大きなメリットが得られます。
たとえば「住宅特定改修特別税額控除」では、バリアフリー改修にかかった費用の一定割合(最大20万円まで)を、所得税から控除することが可能です。
この制度の対象になるには、リフォーム対象の住宅が自己居住用であること、改修の主目的がバリアフリー化であること、そして入居者が高齢者、要介護者、または障害者であることが基本条件となります。
さらに、固定資産税の減額制度も注目です。一定のバリアフリー改修を行った住宅については、翌年度の固定資産税が3分の1に軽減されるという優遇措置があります。こちらも各自治体が定める基準や手続き方法があるため、事前に確認することが重要です。
これらの制度は、リフォーム費用の一部を「税額として取り戻せる」手段として非常に有効です。ただし、申請には「工事証明書」や「住宅の登記事項証明書」などが必要になることも多いため、リフォーム業者とよく相談しながら、早めに準備を進めるようにしましょう。
バリアフリーリフォームの補助金制度
もう一つ注目すべきは、実際にリフォーム費用の一部を補助してくれる「補助金制度」の活用です。なかでも代表的なのが、「介護保険に基づく住宅改修費支給制度」です。この制度では、介護認定を受けている方(要支援・要介護)を対象に、最大20万円までのリフォーム費用が支給されます。
対象となる工事には、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更など、日常生活を安全に送るために必要な改修が含まれます。
補助金は実費の9割(上限18万円)まで支給され、自己負担は実質2万円程度で済むことも多く、非常に利用価値が高い制度です。
また、自治体独自の支援制度も見逃せません。多くの市区町村では、高齢者福祉や障害者支援の一環として、バリアフリーリフォームに対して補助金を交付しています。
中には、介護認定がなくても対象となる制度や、所得制限が緩やかな地域もありますので、お住まいの自治体の窓口に確認することをおすすめします。
これらの制度は、予算に達し次第終了するケースもあるため、「利用できるかもしれない」と思ったら、すぐに情報収集を開始することがカギです。申請のタイミングを逃さないよう、リフォームの計画と並行して補助金の申請準備を行うのが理想的です。
バリアフリーリフォームは、単なる支出ではなく、将来の安心を手に入れるための「投資」と考えるべきです。そして、その投資をより少ない負担で実現するためにこそ、減税制度や補助金制度の活用が不可欠です。制度を上手に使いこなすことで、経済的な不安を解消し、納得のいくリフォームを進めることができるのです。
ホープスタイルでは、中古マンションの購入からリノベーションまで一気通貫で行うことができる会社です。
そのため、リフォーム/リノベーション会社では見ることのできない、中古マンション情報をHP上で多数ご覧できるようになっております。
ぜひ一度ホープスタイルのHPまでお越しいただき、自分たちに合った中古マンションをご覧ください。以下のリンクをクリックいただくと、ご覧いただけます。
バリアフリーリフォームの注意点
バリアフリーリフォームは、安全で快適な生活環境を整えるために欠かせない取り組みですが、やみくもにリフォームを行えば良いというものではありません。むしろ、「目的がはっきりしていない」「使う人の立場が考慮されていない」リフォームは、かえって不便さを生む原因となります。
見た目は整っていても、実際に生活する本人が「使いづらい」と感じてしまえば、そのリフォームは失敗と言わざるを得ません。だからこそ、設計や施工の段階で「何のために、誰のために行うのか」を明確にし、慎重に計画を進める必要があります。
ここでは、バリアフリーリフォームを行う上で特に注意すべき3つのポイントを紹介します。どれも見落とされがちですが、非常に重要な視点です。
「段差解消」だけでない危険回避のバリアフリー

バリアフリーと聞くと、真っ先に「段差のない家」を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに段差の解消は転倒予防に直結する大切な要素ですが、それだけで安全が確保されるわけではありません。
たとえば、段差をなくして床をフラットにしても、滑りやすい床材を使っていては意味がありません。また、移動距離が長くなるような間取りでは、高齢者や体の不自由な方にとっては負担が増すだけです。つまり、「段差の有無」に目を向けるだけでなく、「全体の動線設計」や「素材選び」「生活パターンの見直し」まで含めた包括的な視点が必要になります。
本当の意味でのバリアフリーとは、単に「物理的な障害を取り除く」だけでなく、「心理的にも安心して生活できる空間」をつくることです。視覚的なわかりやすさ、音や光の配慮、プライバシーの確保など、あらゆる面からのリスク回避が求められるのです。
手すりは使い勝手を考えた設置を
手すりの設置はバリアフリーリフォームの定番ですが、その位置や形状を誤ると、逆に使いづらくなってしまうこともあります。よくある失敗が、「とりあえずつけた」というパターン。見た目は整っていても、利用者の身長や体格、動きのクセに合っていなければ、日常動作の補助にはなりません。
たとえば、階段の手すり一つを取っても、右利きか左利きかによって持ちやすい位置が変わりますし、体の支え方も異なります。さらに、握力の強さや関節の可動域なども加味しなければ、手すりをつけたのに「かえって危ない」という逆効果になることもあります。
また、浴室やトイレなどの水回りは、手すりの材質や設置方法にも工夫が必要です。濡れても滑りにくく、寒暖差による結露にも強い素材を選び、握りやすい形状にすることが求められます。
つまり、手すりは「安全の象徴」ではなく、「生活動作を自然に補助するための道具」として考えるべきです。専門家による正確な位置決めや、使う人の声を反映した設計が、失敗しないポイントです。
握力の低下など機能の変化を考慮
高齢者の生活支援において見落とされがちなのが、「加齢に伴う身体機能の変化」です。特に、握力や腕の可動域、反射速度の低下は、日常の何気ない動作に大きな影響を及ぼします。
たとえば、ドアノブの形状ひとつでも、従来の丸型ノブは握力の弱い方には回しづらく、開け閉めが困難です。これをレバーハンドルに変更するだけで、操作性は格段に向上します。また、収納の扉や引き出しも、軽い力で開閉できるソフトモーション型を選ぶことで、ストレスを大きく軽減することができます。
さらに、立ち上がり動作を補助するための椅子の高さや、洗面台の形状、照明スイッチの位置なども、機能変化を前提に調整すべきです。「今はできるから大丈夫」ではなく、「将来的に難しくなるかもしれないこと」を想定することで、バリアフリーリフォームの効果は格段に高まります。
このように、目に見えない変化に寄り添った設計が、真の意味でのバリアフリーを実現する鍵となるのです。
バリアフリーリフォームは、見た目を整えるだけの工事ではありません。そこには「人の動きに寄り添う設計」と「将来への備え」が必要です。段差の解消や手すりの設置といった表面的な対策にとどまらず、一歩踏み込んだ視点で計画することで、誰にとってもやさしい住まいが生まれます。
バリアフリーリフォームの主な工事内容とその効果
バリアフリーリフォームを検討する際、「どんな工事が必要になるのか」という疑問は非常に多く寄せられます。大規模な改修が必要だと思い込んでしまう方も多いですが、実際にはご家庭の状況に合わせて、比較的シンプルな工事でも大きな効果を得ることができます。
ここでは、バリアフリーリフォームの代表的な工事内容をいくつか取り上げ、それぞれがどのような効果をもたらすのかを解説していきます。単なる設備の入れ替えではなく、「生活の質を向上させる」ための選択であるという視点からご覧ください。
手すりの設置
手すりの設置は、もっとも基本的かつ重要なバリアフリー工事の一つです。
転倒リスクの高い場所に手すりを設置することで、自立した動作が可能になり、万が一の事故も未然に防ぐことができます。
特に階段、浴室、トイレなどの移動や姿勢変化が伴う場所では、身体を支える支点があることで、安心感がまったく違ってきます。また、高齢者だけでなく、子どもや妊婦、ケガをしている家族にも役立つ設備です。
設置にあたっては、単に「ある」だけでは意味がありません。握りやすい太さや素材、体格や動線に合わせた位置の調整など、細かな設計が非常に重要です。適切な場所に適切な手すりを設置することで、生活の安全性が飛躍的に向上します。
段差の解消
室内のわずかな段差が、大きな事故の原因になることをご存知でしょうか?
5cmにも満たない小さな段差でも、加齢に伴う脚の上がりづらさや視力の低下によって、つまずきや転倒を引き起こすケースが増えています。
段差解消の方法は、床をかさ上げしてフラットにしたり、逆にスロープを設けて段差をなだらかにしたりと、住宅の構造に応じてさまざまです。玄関や廊下、浴室の出入口など、日常的に出入りが多い場所から優先的に行うのが効果的です。
段差がなくなることで、車椅子や歩行補助具の利用もスムーズになり、移動の自由度が格段に上がります。何より、家の中のすべての移動が「安心してできる」ということは、心理的にも大きな支えになるのです。
滑りにくい床材への変更
意外と見落とされがちなのが、床材の滑りやすさです。
特にフローリング材やタイル材は見た目が美しく掃除もしやすい反面、滑りやすいという特性があります。足腰の弱った高齢者にとって、これは大きな危険因子になります。
バリアフリーリフォームでは、滑りにくく、かつ柔らかさのある素材(例:クッションフロアやノンスリップ加工済みのフローリング)への変更が有効です。また、水回りでは防水性と滑り止め効果を兼ね備えた床材を選ぶことが求められます。
こうした床材への変更は、事故防止だけでなく、足への負担軽減や歩行時の安定性向上にもつながります。滑らない安心感は、日々の暮らしの中で思っている以上に大きな意味を持つのです。
ドアの変更
ドアの種類や開閉方式も、日常動作のしやすさに直結します。
特に高齢者や車椅子利用者にとって、一般的な「開き戸」は使い勝手が悪く、狭い空間では通行の妨げにもなります。こうした問題を解消する方法が、「引き戸」への変更です。
引き戸であれば、少ない力で開閉できるうえ、通路幅も確保されやすくなります。開けた状態を保てるので、介助が必要な場面でもスムーズな動線が確保できます。また、レールの段差がないフラットレールタイプであれば、さらに安全性が向上します。
ドアノブの変更もポイントです。丸型からレバー型に変えることで、握力の弱い方でも簡単にドアの開閉ができるようになります。これもまた、ほんの少しの工事で日常生活の質を大きく向上させる施策のひとつです。
工事内容は見た目以上に多岐にわたりますが、それぞれが「安全」「自立」「快適さ」を実現するための重要な役割を担っています。小さな変更であっても、暮らしのなかでの効果は絶大です。ご家族の年齢や身体状況、将来の生活設計に合わせて、どの工事を優先すべきかをよく検討し、的確なリフォーム計画を立てていくことが大切です。
バリアフリーリフォームを上手に進めるポイント
バリアフリーリフォームは、単なる工事という枠を超えた「暮らしの再設計」です。だからこそ、後悔しないためには事前の準備と正しい知識が不可欠です。
どんなに良い設備や素材を使っても、計画が甘ければ使い勝手が悪くなり、コストだけがかかることになりかねません。ここでは、リフォームを成功させるために押さえておくべき重要なポイントを紹介します。
リフォーム工事の種類を以下でまとめておりますので、一度ご参考にしてみてください。
参考記事:
窓リフォームで補助金を活用して省エネと快適さを両立できる2025年最新支援制度まとめ
水回りリフォームの費用を徹底解説!相場や節約術までわかりやすく紹介
内装リフォームを成功させるための費用相場と施工の流れや注意点まで徹底解説
バリアフリーリフォームの実績が豊富な業者に依頼する
業者選びは、バリアフリーリフォームの成否を左右する最重要ポイントです。
リフォーム業者と一口に言っても、専門性は大きく異なります。バリアフリーに特化した実績を持つ業者でなければ、加齢や介護のリアルな課題に対応した設計は困難です。
実績が豊富な業者は、福祉住環境コーディネーターなどの資格者が在籍していることが多く、現場でのヒアリングから設計、施工、申請手続きまで一貫して対応できます。特に補助金や減税の手続きに詳しい業者は、経済的な負担を抑えるサポートもしてくれるため、心強い存在となります。
選定時には「過去の施工事例」や「利用者の声」を確認するほか、現地調査の際の対応を見て判断するのも良いでしょう。信頼できる業者との出会いが、成功の第一歩となります。
リフォーム箇所は予算と優先順位を考慮して決める
バリアフリー化したい箇所が多いほど、費用も工期もかかります。
すべてを一度にリフォームするのが理想かもしれませんが、現実的には予算や生活への影響を考慮する必要があります。
そこで大切なのが「優先順位」の設定です。まずは転倒リスクが高い浴室や階段、トイレなどから着手し、徐々に範囲を広げていくのが賢明な方法です。
また、現状だけでなく将来の生活スタイルや家族構成も視野に入れて検討することが重要です。
リフォーム会社とともに中長期的なプランを立て、「今必要なこと」と「将来的に備えること」のバランスをとることで、無理のない進め方が可能になります。
工事計画を早めに立てる
介護や体調の変化は、ある日突然やってくることもあります。
そんなときに慌ててリフォームしようと思っても、良い業者にすぐ依頼できるとは限りません。補助金の申請手続きや、材料の発注・工期調整などもあり、思いのほか時間がかかるのが現実です。
だからこそ、「元気なうちに備える」ことが大切です。バリアフリーリフォームは予防的に行うことで、生活の質を維持しやすくなります。特に持病があったり、介護が見込まれる家族がいる場合には、余裕をもってスケジュールを組むことをおすすめします。
余裕のある時期に進めることで、デザインや使い勝手にも納得いく選択ができるため、仕上がりにも満足しやすくなります。
日常生活を1階で済ませられるようにする
年齢とともに階段の上り下りは身体的な負担になります。
2階建ての家に住んでいる場合でも、可能であれば「1階で完結する生活」を目指すことが、バリアフリーリフォームの理想形です。
具体的には、1階に寝室を移設する、トイレや洗面所を新設する、浴室を使いやすく改修するといった方法があります。こうすることで、移動距離や段差の回数が減り、日常生活がより安全かつスムーズになります。
また、将来的に介護が必要になった際にも、1階にすべての生活機能がそろっていれば、在宅介護もしやすくなり、家族の負担も軽減されます。設計段階で「今の暮らし+将来の介護」をセットで考えることが、後悔しない住まいづくりにつながるのです。
バリアフリーリフォームは、単に設備を変えるだけでなく、暮らしそのものを見直すチャンスでもあります。成功のカギは、「計画性」と「専門家との連携」。自分たちにとってベストな選択をするために、正しい情報と判断を積み重ねていきましょう。
【工事箇所別】バリアフリーリフォームの費用相場
バリアフリーリフォームを計画する上で、「どのくらい費用がかかるのか?」という点は最も気になるポイントです。全体像を把握せずに工事に踏み切ってしまうと、想定以上の出費になったり、必要な箇所に十分な予算を割けなくなるリスクもあります。
そこで重要なのが、工事箇所ごとの費用相場をあらかじめ知っておくことです。以下では、住宅内の代表的なリフォーム箇所について、それぞれの特徴とおおよその費用目安を詳しく紹介します。リフォーム計画の参考にしてください。
浴室のバリアリフォームの費用相場
浴室は、家庭内でもっとも事故が起こりやすい場所の一つです。滑りやすい床、またぎにくい浴槽、急な温度差など、さまざまなリスクが存在します。
バリアフリー化においては、以下のような工事が一般的です:
- 滑りにくい床材への変更
- 浴槽の低床化または手すり付き浴槽への交換
- 脱衣所との段差解消
- 引き戸への交換
- 浴室暖房機の設置
これらすべてを含めたフルリフォームの場合、費用は約60万円〜150万円程度が相場です。ただし、部分的な改修であれば20万円〜50万円前後に抑えることも可能です。
トイレのバリアリフォームの費用相場
トイレは、立ち座りの動作が多く、狭い空間での転倒リスクが高い場所です。バリアフリー化の内容としては、以下のようなものがあります:
- 手すりの設置
- 便座の高さ調整
- 洋式トイレへの変更
- 引き戸やスライドドアへの交換
- スペースの拡張
これらの工事を行う際の費用相場は、10万円〜50万円程度です。トイレの新設や拡張などを伴う場合は、さらに費用がかさむこともあります。
玄関のバリアリフォームの費用相場
玄関は、出入りのたびに段差を乗り越える必要があるため、特に高齢者にとっては負担の大きい箇所です。工事の内容としては以下が挙げられます:
- 段差の解消(スロープの設置)
- 手すりの設置
- 玄関土間の拡張
- 引き戸への交換
費用はおおむね30万円〜80万円ほど。外構との接続部分に手を加える場合は、さらに費用がかかる場合がありますが、安全性を高める上で重要な投資と言えるでしょう。
廊下・階段のバリアリフォームの費用相場
廊下や階段は、住まいの中でも日常的に何度も通る場所でありながら、転倒リスクが高くなりがちなエリアです。以下のような工事が行われます:
- 手すりの取り付け(両側設置が望ましい)
- 滑り止め加工付きの床材への変更
- 照明の増設(センサー付きライトなど)
これらの費用は、15万円〜40万円程度が目安です。階段の構造によっては追加の補強工事が必要な場合もあり、見積もりの際には詳細な調査が必要となります。
キッチンのバリアリフォームの費用相場
キッチンにおけるバリアフリーは、「安全」と「効率性」の両立が求められます。主な内容は以下のとおりです:
- 高さ調整可能なシステムキッチンへの交換
- 床材の滑り止め加工
- 通路幅の拡張(車椅子対応)
- 引き出し式収納の導入
これらの改修を含めた場合、費用相場は70万円〜150万円程度です。設備のグレードによって金額は変動しますが、将来の介護対応も視野に入れた設計が重要です。
洗面所・脱衣所のバリアリフォームの費用相場
洗面所や脱衣所は、動作が多く温度差の影響も受けやすい場所です。以下の工事がよく実施されます:
- 滑りにくい床材の導入
- 洗面台の高さ調整
- 手すりの設置
- 換気・暖房設備の設置
費用相場は、20万円〜60万円ほどです。浴室との連携を意識した設計にすることで、安全性がさらに高まります。
寝室のバリアリフォームの費用相場
寝室は、一日の始まりと終わりを過ごす場所であり、安心して休める環境が不可欠です。以下のような改修が対象です:
- ベッド周りの手すり設置
- 車椅子移動用のスペース確保
- スイッチや照明の位置変更
- 断熱性の向上
寝室のリフォーム費用は15万円〜50万円程度が相場です。介護ベッドなどを利用する場合には、それに応じたスペース設計が必要になります。
バリアフリーリフォームの費用は、工事内容や住宅の構造、地域によって変動しますが、部分的な工事からでも始めることが可能です。まずは専門家に相談し、自分たちに必要な工事と予算感を明確にすることが、納得のリフォームへの第一歩となります。
今、スケルトンリフォームが人気沸騰中ということをご存知でしょうか?そんなスケルトンリフォームについて詳しく解説しておりますので、ここで一度ご確認ください。
関連記事:スケルトンリフォームとは何か知りたい人のためにメリットデメリット費用や流れまでを徹底解説
バリアフリーリフォームの工事内容と費用相場まとめと今後の検討ポイント
バリアフリーリフォームは、家族全員が「安全・快適・自立的」に暮らすための住環境を整えるものです。これまで見てきたように、工事内容は多岐にわたり、それぞれの場所に応じて適切な配慮と設計が求められます。ここでは、バリアフリーリフォームにおける主要な工事項目と費用相場を改めて整理するとともに、今後リフォームを検討するうえで押さえておくべき実践的なポイントをご紹介します。
バリアフリーリフォームの主要工事と費用のまとめ
バリアフリーリフォームには、場所ごとに特有のリスクと、それに対応する具体的な工事内容があります。以下に、代表的なリフォーム箇所ごとの内容と費用の目安を一覧にまとめました。
|
リフォーム箇所 |
主な工事内容 |
費用相場(目安) |
|
浴室 |
滑りにくい床材、浴槽の低床化、手すり、引き戸、浴室暖房 |
40〜100万円 |
|
トイレ |
洋式便座への変更、手すり、スペース拡張、引き戸化 |
15〜50万円 |
|
玄関 |
スロープ、手すり、滑り止め、玄関ドアの交換 |
20〜80万円 |
|
廊下・階段 |
両側手すり、滑り止め加工、照明設置 |
10〜40万円 |
|
キッチン |
高さ調整、引き出し収納、IH化、滑りにくい床材 |
60〜120万円 |
|
洗面所・脱衣所 |
断熱、手すり、防滑床、洗面台の高さ調整 |
15〜50万円 |
|
寝室 |
手すり、スイッチ位置変更、断熱、介護対応動線確保 |
10〜40万円 |
※上記は一般的な戸建・マンションにおける相場であり、地域や住宅の構造によって異なる場合があります。
費用面を正しく捉えるポイント
バリアフリーリフォームの費用については、「全体で100万円〜300万円程度かかるのでは」と不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、すべての工事を一度に行う必要はありません。優先順位を明確にして、段階的に進めていくことが可能です。
また、以下のような補助制度や減税措置を活用すれば、実質的な自己負担額を大きく抑えることができます:
- 介護保険による住宅改修費支給(最大18万円)
- 所得税のバリアフリー改修控除(最大20万円)
- 固定資産税の軽減措置(1/3減額)
- 地方自治体の補助金(自治体により異なる)
制度を活用するには、「工事前に申請が必要なもの」が多いため、必ず専門業者と連携しながら進めることが重要です。
工事計画における実践的な検討ポイント
バリアフリーリフォームを成功に導くためには、単に「必要な工事をする」だけでなく、生活全体を見直したうえでの計画が求められます。以下に、具体的な検討ポイントを挙げます。
■ ① 優先順位を明確にする
最も事故が起きやすい場所(浴室、トイレ、階段)から優先的に対応しましょう。すべてを同時に行う必要はありません。
■ ② 将来の介護や同居を見越した設計
例えば、将来的に車椅子生活になる可能性がある場合は、廊下や出入口の幅を広げることを検討しましょう。同居予定の親の状況を踏まえた設計も大切です。
■ ③ 「使う人に合わせる」ことを最優先に
手すりの高さ、ドアの位置、収納の使いやすさなど、住む人の体格や動作に合わせて設計することで、真のバリアフリーが実現します。
■ ④ 業者選びは慎重に
バリアフリーの実績が豊富で、福祉住環境コーディネーターなどの資格者が在籍している会社を選ぶと、要望が伝わりやすく、補助金制度のアドバイスも受けられます。
バリアフリーリフォームで実現する「安心と自立」
リフォームというと「老後の備え」として捉えがちですが、バリアフリー化は「より良い暮らしへの前向きな投資」でもあります。加齢による身体の変化に先回りして備えることで、将来の不安が大きく軽減されるだけでなく、日々の生活にも安心感が生まれます。
また、自分のことを自分でできる環境を整えることは、高齢者の「自立意欲」を支えます。これは精神面での健康維持にもつながり、結果的に家族の介護負担の軽減にもつながります。
今すぐ始めるべきは「相談と情報収集」
「まだ必要ない」と思っている今こそが、最もリフォームに適したタイミングです。介護が始まってからでは遅く、希望通りの改修ができないケースも多くあります。
- 家族と話し合う
- 地元の自治体に相談する
- 専門業者に現地調査を依頼する
- 補助制度の適用条件を確認する
このように、一つずつステップを踏んでいけば、大がかりなリフォームであっても無理なく進められるはずです。
まとめ|バリアフリーリフォームは「未来を変える住まいの投資」
バリアフリーリフォームは、単なる設備改善ではなく、「人生を支える住まいづくり」そのものです。安全性、快適性、自立性、そして家族の負担軽減——そのすべてを叶えるためには、正しい情報をもとにした計画と行動が不可欠です。
今の住まいを見直し、将来への備えを具体化する第一歩として、まずはプロに相談してみましょう。きっと、今よりもっと暮らしやすい未来が見えてくるはずです。
「ちょっとした相談だけど大丈夫かな..」
ホープスタイルは、そのような簡単な相談も受け付けております。以下のリンクからお問い合わせや、ご相談のご連絡をいただければと思います。


