
近年、「新築にこだわらない住宅購入」が注目されており、リノベーションマンションという選択肢を検討する人が増えています。
「見た目が新築同様」「価格が抑えられる」「立地条件が良い」など、魅力的なポイントが多く存在する一方で、構造の老朽化やローン控除の適用条件といった、知らないと損をするデメリットもあるのが実情です。
本記事では、「リノベーションマンションとは?新築とは違う賢い選択肢である理由を徹底解説」というテーマのもと、メリット・デメリット、選び方のコツ、保証制度まで幅広く解説していきます。
「リノベーションマンションって結局どうなの?」という疑問に明確な答えを出すための情報を、ぜひ参考にしてください。
リノベーションとリフォームの違いについては、こちらの記事をご参考にしてみてください。
参考記事:リフォームとリノベーションの違いとは?メリット・デメリットも解説
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
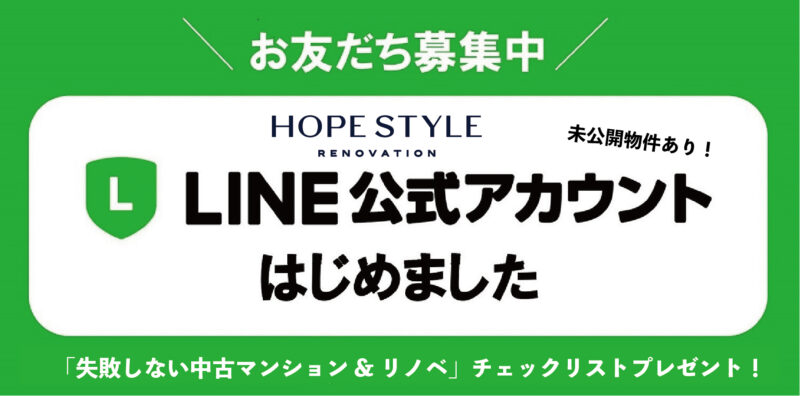
目次
リノベーションマンションとは何かをわかりやすく解説
マンション購入を考える人々の中で、今や「リノベーションマンション」という言葉は決して珍しいものではありません。しかし、「リフォーム」との違いや、「中古マンションと何が違うのか?」といった基本的な疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。
ここでは、リノベーションマンションの本質と魅力について、具体的にわかりやすく解説します。
リノベーションマンションとは、価値を再構築した“新しい中古住宅”
リノベーションマンションとは、築年数が経過した中古マンションを、内装・設備・機能性を一新することで、まるで新築のような状態に再生した物件を指します。単に古い部屋を綺麗にするのではなく、「住宅の価値そのものを再設計」することがリノベーションの目的です。
生活スタイルに合った空間にアップグレードできるから
現代のライフスタイルは、従来の住宅設計ではフィットしない場面も多く見られます。
例えば、「在宅ワーク向けのワークスペースを作りたい」「広々としたLDKで家族との時間を過ごしたい」などのニーズに対して、築古物件では対応が難しいことがあります。
そこでリノベーションが選ばれるのです。配管や電気系統などの見えない部分から手を入れ、間取りやデザインをフルカスタマイズできることで、自分のライフスタイルにぴったりの住まいが実現します。
築30年の物件が、まるでホテルライクな空間に変身
例えば、築30年以上経過したマンションを購入し、スケルトン状態(骨組みだけの状態)からフルリノベーションを施したケースでは、モダンな内装・最新のキッチン設備・断熱性の高い窓ガラスなどが導入され、まるで高級ホテルのような空間に仕上がることもあります。
また、耐震補強や断熱工事が施されている物件であれば、住み心地と安心感も新築と遜色ありません。
中古の枠を超えた、魅力的な選択肢が“リノベマンション”
このように、リノベーションマンションは「中古住宅」の枠を超えた存在です。古いものを活かしながら、新たな価値を吹き込む——それがリノベーションの本質です。
自分らしい暮らしを実現しながら、価格面でも合理的な選択ができる点が、現代の住宅購入者から支持を集めている理由です。
リノベーションマンションとはどういったメリットがあるのか
リノベーションマンションを選ぶ人が増えている背景には、明確なメリットが存在します。価格の安さだけでなく、立地や居住性、即入居可能といった実用的な利点まで、さまざまな角度から魅力を感じられるのがリノベーションマンションの強みです。以下では、その主なメリットを深掘りしてご紹介します。
価格が新築マンションよりも安価な傾向にある
リノベーションマンションは、同じエリアの新築マンションと比較して、購入価格が抑えられる傾向にあります。
物件自体は中古であるため、新築のような高い広告費や建設費が価格に上乗せされることが少なく、コストを抑えて購入することが可能です。また、リノベーション後であっても「中古扱い」となるため、固定資産税などの税負担も比較的軽く済みます。
例えば、東京都内で70㎡の新築マンションを購入する場合、平均価格は7,000万円を超えるケースも珍しくありません。一方、同じエリアで築20〜30年の物件をリノベーションしたマンションであれば、5,000万円台で購入できることもあり、2,000万円近い差が生じることもあります。
購入コストを抑えつつ、質の高い住環境を手に入れられるリノベーションマンションは、コスト重視のユーザーにとって非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
好立地の物件を選びやすい
リノベーションマンションは、新築よりも立地条件に優れた物件が多く、生活利便性の高い場所に住むチャンスがあります。
多くの新築マンションは、郊外や再開発地域に集中する傾向がありますが、リノベーション対象となる中古物件は、すでに開発された都市中心部や駅近など、利便性の高いエリアに多く存在しています。そのため、「立地」を最優先に考える場合、リノベーション物件の方が選択肢が広がります。
都内のターミナル駅から徒歩5分圏内の新築物件は、供給数が限られ価格も高額になりますが、築30年以上の中古物件であれば、そのような好立地でも見つかる可能性があり、リノベーションによって内部を一新すれば、まさに“場所良し・中身良し”の物件に変貌します。
生活利便性や資産価値を重視する人にとって、立地に優れたリノベーションマンションは、新築以上の満足度を提供してくれるかもしれません。
購入後すぐに入居できる
リノベーションマンションは基本的にリフォーム済みで販売されるため、契約後、短期間で入居が可能です。
新築マンションの場合は完成前に契約する「青田売り」が多く、引渡しまでに数ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。一方、リノベーションマンションはすでに建物が存在しており、工事も完了済み。契約から1ヶ月程度で引越しができるケースがほとんどです。
特に、転勤や子どもの入学など、タイミングが限られる状況では、入居時期を調整できない新築よりも、すぐに住めるリノベーションマンションが有利になります。内見したその日に「住むイメージ」が具体化できるのも利点です。
急ぎで引越しを検討している方や、生活のスケジュールに合わせて住まいを選びたい方には、リノベーションマンションの「即入居可」は非常にありがたいポイントです。
中古マンションの購入については、こちらの記事からご覧いただけます。
関連記事:中古マンションを購入する流れとは。住宅ローン・現金で買う場合、購入と同時にリフォームする場合の流れや必要な期間を解説
内装や設備が新築と同等レベルにアップグレードされている
リノベーションマンションは、内装や住宅設備に最新技術を取り入れており、住み心地は新築と遜色ありません。
フルリノベーションされた物件では、キッチン、浴室、トイレ、床材、壁材などすべてが刷新され、現代のトレンドを反映した仕様となっています。また、省エネ設備や最新のセキュリティシステムが導入されている物件も多く、生活の快適さが格段にアップします。
最新のIHクッキングヒーターや食洗機、浴室乾燥機付きバスルーム、二重サッシによる防音・断熱性能などが備わっている物件は、まさに“新築以上”の住環境といえるでしょう。
「古い物件=使いにくい」という先入観は、現代のリノベーション事情においては通用しません。リノベーションマンションは、“見た目だけでなく中身も新築並み”であるという点に注目すべきです。
リノベーションマンションとはどういったデメリットがあるのか

リノベーションマンションは魅力が多い一方で、注意しなければならないポイントも存在します。
見た目は新築のようでも、実際には築年数が経過している物件であることに変わりはありません。ここでは、リノベーションマンションの主なデメリットと、それらへの対策について詳しく解説します。
構造体や配管など見えない部分の老朽化リスク
リノベーション済みであっても、建物全体の構造や配管といった見えない部分に老朽化のリスクが残っている可能性があります。
リノベーションは多くの場合、内装や設備といった“目に見える部分”に重点が置かれています。しかし、給排水管や電気配線などのインフラ、そして柱や梁といった構造体までリニューアルされているとは限りません。これらの劣化が放置されていると、後々トラブルや大規模修繕が発生するリスクが高くなります。
築40年のマンションで、室内は完全にリノベーションされていたものの、数年後に排水管の腐食が見つかり、住戸内の大規模な再工事が必要となった例もあります。こうしたケースでは、修繕費用を個人で負担しなければならない場合もあり、思わぬ出費につながります。
購入前には、物件のインフラ部分の改修履歴や、マンション全体の大規模修繕計画を必ず確認しましょう。構造や配管にまで手が入っているリノベーション物件を選ぶことが、安心な住まいへの第一歩です。
耐震基準に注意が必要
リノベーションマンションを選ぶ際は、耐震性が現行の基準に合っているかどうかを確認することが重要です。
日本では1981年に建築基準法が改正され、新耐震基準が施行されました。この基準を満たしていない建物は、大地震時に倒壊のリスクが高いとされ、住宅ローンの審査にも影響する可能性があります。リノベーションは見た目や設備の刷新を中心に行われるため、構造の補強がされていない場合も多いのです。
築年数が古く旧耐震基準で建てられた物件を購入したものの、自治体の耐震診断で「倒壊の可能性がある」と判断され、結局取り壊しに至ったというケースもあります。こうなると物件の資産価値は大きく損なわれ、売却も困難になります。
物件の築年や耐震診断結果、新耐震基準の適用状況を確認し、「見た目は新しいが中身は旧基準」という事態を避けるようにしましょう。
物件によって間取りの変更ができない場合がある
全てのリノベーションマンションが自由に間取り変更できるとは限らず、構造上の制限がある場合もあります。
マンションの構造が「ラーメン構造」ではなく「壁式構造」であったり、耐震壁があると、撤去できない壁が存在し、自由な間取り変更が不可能になります。また、既にリノベーション済みで販売されている物件は、購入者の好みに応じて変更することができないケースが多く、自分の理想を完全に反映させるのが難しいのです。
「広々としたLDKを希望していたが、壁式構造のため間取り変更ができず、家具配置に困ってしまった」といった不満の声も少なくありません。見た目はモダンでも、暮らし方とのミスマッチが生まれる可能性があります。
内覧時や契約前に、構造の種類と間取り変更の可否をしっかり確認し、自分のライフスタイルに合った間取りであるかを判断しましょう。
住宅ローン控除などの制度が適用されにくいケースがある
リノベーションマンションは、住宅ローン控除やその他の税制優遇が受けられない場合があり、注意が必要です。
住宅ローン控除を受けるには、築年数や物件の状態、リノベーションの工事内容が一定の基準を満たしていなければなりません。
特に木造で築20年超、鉄筋コンクリートで築25年超の物件は、耐震基準を満たしていないと控除の対象外になる可能性があります。また、リノベ済み物件を「再販業者」から購入する場合、売主が法人でないと控除対象外となることもあるため、複雑な条件が絡んできます。
住宅ローン控除を前提に資金計画を立てていたが、後から控除対象外であることが判明し、月々の返済負担が予想より増えてしまった、というケースも報告されています。
住宅ローンや控除制度の適用条件については、必ず金融機関や専門家に事前に相談しましょう。制度の仕組みを正しく理解することが、後悔のない物件購入につながります。
築年数が古い中古マンションの住宅ローンについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:築年数が古くても中古マンションで住宅ローン控除を受けるための条件と注意点を徹底解説
物件を見たい!そんな方は、以下のリンクから中古マンション物件をご確認ください。
リノベーションマンションとは何が新築物件と違うのか
リノベーションマンションと新築マンションは、どちらも魅力的な住まいの選択肢ですが、その本質や特徴には明確な違いがあります。購入時の判断材料として、この違いをしっかり理解しておくことは極めて重要です。ここでは価格・費用・工期という3つの観点から比較し、それぞれの特徴を詳しく解説します。
①物件の価格
リノベーションマンションは、同じ立地・広さで比べた場合、基本的に新築よりも価格が安く設定されています。
新築マンションは土地取得費や建築費、広告宣伝費などが物件価格に上乗せされるため、どうしても価格が高くなりがちです。一方、リノベーションマンションは中古物件をベースにしているため、建物自体の価値が下がっていることが多く、総額として割安になります。
都心部で新築マンションを購入しようとすると、70㎡の3LDKで最低でも7,000万円〜8,000万円はかかることが一般的です。しかし、同じエリアで築30年程度の中古マンションをリノベーションした場合、5,000万円台で購入できるケースもあります。つまり、2,000万円以上の価格差が生まれることもあるのです。
価格重視で物件を探す場合には、リノベーションマンションの方が圧倒的に選択肢の幅が広くなります。特に同じ立地で比較した際のコストパフォーマンスの高さは見逃せません。
②購入費用や税金の差
新築とリノベーションでは、購入にかかる諸費用や税金にも大きな違いがあります。これを理解しておくことで、総費用を正確に把握できます。
新築物件は建物価格が高いため、それに連動して仲介手数料や登録免許税、不動産取得税も高くなります。加えて、建物部分の消費税も課税される点も見逃せません。一方、リノベーションマンションは中古住宅として扱われるため、非課税部分が多く、諸費用を大きく抑えることが可能です。
3,000万円の新築マンションと3,000万円のリノベーションマンションを購入した場合でも、諸費用を含めた総支出は50万〜100万円ほどリノベーション物件の方が安くなる可能性があります。特に住宅ローンの事務手数料や登記関連費用の差は大きく、見落とされがちな費用の削減に繋がります。
購入価格だけでなく、諸費用まで含めた「総額」で比較することで、リノベーションマンションの費用面での優位性がより明確になります。
③工期や入居までのスピード
リノベーションマンションは、購入から入居までのスピード感が早く、ライフスタイルに応じた柔軟な対応が可能です。
新築マンションは、完成前に販売が始まる「青田売り」が主流で、実際に入居できるのは1年〜1年半後になることも珍しくありません。それに対してリノベーションマンションは、リフォーム工事がすでに完了している物件が多いため、契約から1ヶ月前後で引き渡し・入居が可能です。
「急に転勤が決まった」「子どもの入学時期に合わせたい」など、タイムリミットがあるケースでは、スピード入居できるリノベーションマンションが圧倒的に有利です。また、内見したその日に「この部屋に住む」という具体的なイメージが湧くのも、完成済み物件ならではの魅力です。
入居時期が明確に決まっている、あるいはなるべく早く住み替えたいというニーズを持っている方にとって、リノベーションマンションは非常に現実的で柔軟性の高い選択肢です。
リノベーションマンションとはどちらを選ぶか迷った時の判断ポイント
マンションの購入を検討していると、必ずぶつかるのが「新築にするか、リノベーションマンションにするか」という選択です。どちらにもメリットとデメリットがあるため、一概にどちらが優れているとは言い切れません。しかし、選択を誤ると、将来的に後悔してしまう可能性もあるため、自分にとっての最適解を見つけることが重要です。このセクションでは、判断のための具体的な基準と考え方を詳しく解説します。
ライフスタイル・予算・価値観の3軸で判断しよう
新築かリノベーションかを選ぶ際は、「現在と未来のライフスタイル」「資金計画」「価値観や優先順位」の3つを軸に考えることが有効です。
“自分にとっての正解”は人によって異なるから
新築マンションは最新設備や高性能な建材、耐震性能、アフターサポートの充実など、多くの安心感を提供してくれます。一方、リノベーションマンションは価格を抑えながらも、立地や内装の自由度、入居のスピードといった点で優れています。つまり、どちらも魅力的ですが、「何を重視するか」によって適した選択が変わるのです。
こんな人には新築/リノベがおすすめ
- 新築マンションが向いている人
→将来にわたり長く住み続けたい/最新の省エネ・セキュリティ設備を重視する/保証を重視したい - リノベーションマンションが向いている人
→都市中心部に住みたい/予算を抑えたい/すぐに入居したい/自分らしい空間に住みたい
例えば、小さなお子様がいるファミリー層で、耐震性や環境性能を重視する方には新築がおすすめです。一方、DINKs(共働き夫婦)や単身者で、利便性の高い立地や価格のバランスを重視する方は、リノベーションマンションの方が満足度が高い場合もあります。
「何を譲れないか」を明確にすることが最良の選択につながる
自分自身や家族の「譲れない条件」を洗い出すことで、どちらがより理想に近いのかが自然と見えてきます。見た目や価格だけでなく、10年・20年先の暮らしまで見据えて選択することが、後悔しない家選びにつながるでしょう。
物件選びの際のポイント
リノベーションマンションを選ぶ際には、見た目の美しさや価格だけで判断するのは危険です。長く快適に住むためには、築年数や修繕計画、管理状態など、物件の“中身”を見極める視点が欠かせません。ここでは、失敗しないための物件選びにおいて特に注目すべき3つの視点を紹介します。
①購入費用・修繕費用
購入費用だけでなく、入居後に発生する修繕費用も含めてトータルコストで考えることが大切です。
多くの購入者は物件価格ばかりに目を向けがちですが、実際には毎月の管理費・修繕積立金、将来的な大規模修繕費用など、維持コストも住まい選びの重要な要素です。これらが不十分に設定されていると、あとから予想外の出費に悩まされることになります。
例えば、購入当初は管理費・修繕積立金が安く設定されていても、築年数が経過しているマンションでは今後の費用が急激に上がるケースもあります。また、必要な修繕が先送りされていると、資産価値の低下や居住環境の悪化を招く恐れもあります。
予算を考えるときは、目先の価格だけでなく「5年後、10年後にかかるコスト」も含めて総合的に比較検討することが、賢い買い方といえるでしょう。
②築年数
築年数は物件選びの基本。表面だけでなく「いつ建てられたか」をしっかり確認しましょう。
築年数が古いほど、建物自体の劣化や修繕の必要性が高くなります。また、1981年以前に建てられた物件は旧耐震基準で建てられている可能性があり、安全性の観点からも注意が必要です。
築40年の物件で、見た目はリノベーションされていても、外壁や共用部分の修繕履歴がなかったために、雨漏りや劣化によるトラブルが多発したという事例もあります。築年数だけでなく、その後どのようなメンテナンスがされてきたかも重要です。
築年数は「目安」であり、実際の管理状態とあわせて確認することで、より安心できる物件選びが可能になります。
③修繕計画や管理組合の現状
物件の将来性を左右するのは、管理体制と修繕計画の有無。これは「見えない資産価値」とも言える重要な要素です。
いくらリノベーションで内装が綺麗でも、マンション全体の管理がずさんであれば、資産価値が下がったり、住環境が悪化したりするリスクがあります。修繕計画がしっかり立てられており、管理組合が機能しているかどうかは、必ず確認しておきたいポイントです。
ある物件では、修繕積立金が不足していたため、外壁の補修が10年近く先送りにされていました。その結果、壁面の劣化が進み、雨漏りなどが発生。住民全員に追加で数十万円の一時金が課せられ、住民トラブルにまで発展したケースもあります。
管理組合の議事録や修繕計画書を確認し、健全な運営がなされているかを見極めることが、長期的に安心して暮らすための大きな鍵となります。
リノベーションマンションにする際の注意点
リノベーションマンションには多くの魅力がありますが、実際に購入を検討する際には、いくつか注意しなければならないポイントも存在します。見た目や価格に惑わされず、将来の生活やトラブルを未然に防ぐためにも、以下のような点をしっかり押さえておくことが大切です。
リノベーション費用は住宅ローンが組みにくい
リノベーションの費用は、すべてが住宅ローンに組み込めるわけではないため、資金計画が複雑になる可能性があります。
中古物件を購入してからリノベーションを行う「自分でリノベ型」の場合、リノベーション費用と物件購入費用を別々に融資申請しなければならないケースも多く、金融機関によっては対応していない場合もあります。また、一体型ローンが利用できるかどうかで、手間や金利条件も大きく変わってきます。
ある購入者は、中古物件購入とリノベ費用を一括でローンに組み込もうとしましたが、金融機関から「リノベ部分は自己資金で」と言われ、結果的に予定よりも多くの頭金を用意する必要がありました。
事前に金融機関と相談し、どこまでローンに組み込めるか、金利や返済条件を確認しておくことで、資金繰りのトラブルを避けることができます。
住宅ローン控除が適用されない場合がある
住宅ローン控除を受けるには一定の条件があり、すべてのリノベーションマンションが対象になるわけではありません。
控除を受けるには、耐震性の基準を満たすことや、適正な施工証明があること、リノベーション工事の完了日や契約日が基準をクリアしていることなど、複数の条件を満たす必要があります。これらを満たしていないと、せっかくローンを組んでも、税金面での恩恵が得られない可能性があります。
築40年のマンションを購入したものの、耐震基準を満たしていないために住宅ローン控除が適用されず、当初予定していた節税額がゼロになってしまったというケースもあります。
控除の適用条件は非常に細かく、個別のケースによって異なるため、税理士や不動産会社に事前に確認しておくことが重要です。
間取りを変えられない物件がある
物件によっては構造的に間取りの変更ができないことがあり、「思い通りのリノベーション」が叶わないケースもあります。
特に壁式構造のマンションや、梁・柱の位置が決まっている物件では、間取りの大幅な変更ができません。すでにリノベーション済みで販売されている物件も多く、その場合は自分好みにアレンジする余地がなくなることがあります。
リビングを広く取りたかったが、壁が構造躯体となっており撤去できなかったため、理想のレイアウトにできなかった、という購入者の声も多くあります。
「自由にリノベできると思っていたのにできなかった」とならないように、間取り変更が可能かどうか、設計前に構造をチェックしておきましょう。
保障制度について
リノベーションマンションを購入する際に、見落としてはいけないのが「保証制度」です。新築マンションと異なり、中古住宅には保証がつかないケースもありますが、最近では買主の安心のために、さまざまな保証制度が整備されつつあります。ここでは代表的な2つの保証制度について、わかりやすく解説していきます。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
瑕疵担保責任とは、購入した住宅に「隠れた欠陥」があった場合、売主が責任をもって修理や損害賠償を行う義務のことです。
見た目には分からない部分に欠陥があった場合、購入者には防ぎようがありません。特に中古住宅では、雨漏りや配管の腐食などが引渡し後に発覚するケースも少なくありません。こうした問題に備えるために、法律で定められているのが「瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)」です。
リノベーション済みの中古マンションを購入し、半年後に天井から雨漏りが発生。原因はリフォーム前の屋根構造の劣化だったが、売主が瑕疵担保責任を認め、補修費用を全額負担した事例があります。これは売買契約書に「瑕疵担保責任2年間」と明記されていたからこそ実現したものです。
契約書をよく確認し、保証内容や期間についてしっかり理解しておくことが、購入後のトラブルを防ぐカギとなります。
適合リノベーション住宅とは
「適合リノベーション住宅」とは、一定の基準を満たし、第三者機関のチェックを受けた高品質なリノベーション物件を指します。
リノベーション住宅は施工品質にばらつきがあり、購入者が判断しにくいのが実情です。そこで、住宅性能評価や一定の検査基準をクリアした住宅に対して「適合リノベーション住宅」として認証する制度が登場しました。これにより、買主は品質の担保された住宅を安心して選ぶことができます。
「R1住宅」や「安心R住宅」など、国土交通省が認定する基準を満たした住宅は、第三者機関によるインスペクション(建物調査)を経て、一定の品質保証がつきます。たとえば、見えない部分の構造・設備にも検査基準があるため、「リノベ済=安心」とは限らない現状に対する信頼性の指標になります。
初めて住宅を購入する人や、建物の安全性に不安を感じる人にとっては、「適合リノベーション住宅」というラベルは、安心の象徴となります。購入時には、こうした認証の有無をチェックする習慣をつけましょう。
リノベーションマンション選びのコツはメリット・デメリットを知ること
リノベーションマンションを検討するうえで、多くの人が魅力的な“見た目”や“価格の安さ”に引かれがちですが、冷静にメリットとデメリットの両面を把握することが、後悔しない住まい選びへの第一歩です。ここでは、その重要性と具体的な判断ポイントについて解説していきます。
判断基準は“両面”を知ることから始まる
どんな物件にも長所と短所はあります。メリットだけに目を向けると、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性も。リノベーションマンションを選ぶ際は、良い点もリスク要因もセットで理解することが大切です。
“住む”という現実は、メリットだけでは語れないから
リノベーションマンションの代表的なメリットには、価格の安さ・立地の良さ・即入居可能・デザイン性の高さなどがあります。一方で、構造部分の老朽化・耐震性・保証範囲の限界・間取りの制約・住宅ローン控除の制限といったデメリットも存在します。こうした情報を知っていれば、後から「こんなことは知らなかった」というトラブルを避けられます。
実際の購入者の声から学ぶ
ある購入者は、「駅近でフルリノベ済み、価格も手ごろ」と理想の条件を満たす物件に飛びつきました。しかし、入居後に配管トラブルが頻発。築年数が40年を超えており、インフラの更新が行われていなかったことが原因でした。事前にインフラや管理状況をチェックしていれば防げた事例です。逆に、デメリットを理解した上で購入した別の人は、「立地も価格も妥協できる点がわかっていたから、納得して住めています」と、満足のいく生活を送っています。
情報を正しく知ることが最大の“武器”になる
リノベーションマンションは、上手に選べばコストパフォーマンスの高い素晴らしい選択肢となります。ただし、“知らなかった”という情報不足は失敗の元。購入前にしっかりと情報収集し、メリットとデメリットの両面を正しく理解することで、満足のいく住まい選びが実現できるでしょう。
リノベーションとリフォームの定義とは
「リノベーション」と「リフォーム」は、似ているようで実は目的や施工内容が大きく異なります。住宅購入や改修を考えるうえで、この2つの違いを明確に理解しておくことは非常に重要です。
誤解したまま進めると、仕上がりや費用、満足度に大きな差が出る可能性もあるため、ここでしっかりと整理しておきましょう。
「リノベーション」と「リフォーム」の違いなどは、こちらからご覧ください。
“リノベ”は価値の再構築、“リフォーム”は原状回復
リフォームは老朽化した部分を「元に戻す」ことを目的とし、リノベーションは住まいの性能や価値を「新たに創る」ことを目的としています。
目的もスケールも異なるからこそ、使い分けが必要
リフォームは部分的な修繕や交換が主で、例えば壁紙の張り替えや設備の交換といった、比較的小規模な工事が中心です。一方リノベーションは、間取りの変更、配管・配線の更新、断熱性能の向上など、住まい全体の機能や価値を根本から見直す大規模な改修です。そのため、設計や施工には建築的な知識と経験が必要とされ、費用や工期も大きく異なります。
水回り交換はリフォーム、間取り変更はリノベーション
例えば、古くなったユニットバスを新しいものに交換するのはリフォームです。しかし、浴室の位置を移動したり、キッチンとLDKをひとつの空間にまとめたりするのは、リノベーションに該当します。つまり、暮らし方そのものを変えるのがリノベーション、元の姿に戻すのがリフォームという位置づけです。
目的に応じて正しく使い分けることが成功への第一歩
リフォームとリノベーションはどちらが良いという話ではなく、「住まいに何を求めるか」によって選択すべき手法が変わってきます。今の家を“直したい”のか、それとも“生まれ変わらせたい”のか——この視点を持つことが、満足のいく住宅計画を進める上で不可欠です。
ホープスタイルでは、中古マンションの購入からリノベーションまで一気通貫で行うことができる会社です。
そのため、リフォーム/リノベーション会社では見ることのできない、中古マンション情報をHP上で多数ご覧できるようになっております。
ぜひ一度ホープスタイルのHPまでお越しいただき、自分たちに合った中古マンションをご覧ください。以下のリンクをクリックいただくと、ご覧いただけます。

