
中古マンションを購入するというのは、多くの人にとって人生の一大イベントです。しかし、購入後に「確定申告をしないと損をするかもしれない」ということをご存知でしょうか?
特に住宅ローンを利用して購入した場合、正しく確定申告を行うことで「住宅ローン控除」という強力な節税制度を利用できます。これにより、毎年数十万円単位で所得税・住民税の負担が軽減される可能性があります。
本記事では、「中古マンション 購入 確定申告」というテーマに基づき、初めての方にも分かりやすく、確定申告の流れ、必要書類、よくあるケース別の対応方法まで詳しく解説していきます。損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
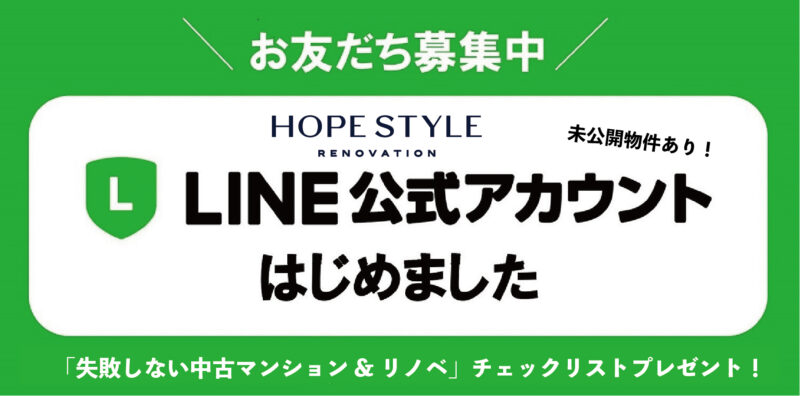
目次
中古マンション購入時に確定申告が必要な理由とは
なぜ確定申告が必要なのか?
確定申告という言葉に苦手意識を持つ人は多いかもしれません。しかし、中古マンションを購入した場合、特に住宅ローンを利用しているなら、「確定申告はしなければ損」と言えるほど重要です。ここではその理由をわかりやすく説明します。
住宅ローンを利用して中古マンションを購入した人は、「住宅ローン控除」を受けるために、購入した年に自ら確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税から差し引くことができる制度です。これにより、所得税が還付されるほか、控除しきれなかった分は住民税の一部にも反映されます。会社員であってもこの控除を利用するには、購入初年度に限って自ら確定申告を行う必要があります。これを怠ると、1年分の控除が受けられなくなり、大きな金銭的損失につながります。
例えば、3,000万円の中古マンションを購入し、2,800万円の住宅ローンを組んだとしましょう。年末残高が2,600万円だった場合、約18万円が所得税から控除される計算になります。これを10年間受けられるとすれば、最大180万円の節税が可能になります。しかし、確定申告をしなければこの控除は1円も受けられません。
確定申告を「面倒だから」と後回しにしてしまうのは非常にもったいないことです。購入初年度の確定申告を確実に行い、住宅ローン控除をしっかり受け取ることが、賢く節税する第一歩です。
確定申告をすることで受けられるメリット
中古マンションを購入して確定申告を行うことには、非常に多くのメリットがあります。金銭的な利点にとどまらず、将来のライフプランにも大きな影響を与えるため、正しい理解が必要です。
中古マンションを購入した際に確定申告を行う最大のメリットは、住宅ローン控除による税金の還付が受けられることです。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に対して一定割合を所得税・住民税から控除する制度です。これにより、年間で10万円〜20万円前後の還付金が発生する可能性があります。しかもこの控除は最長で10年間受けることができ、合計では100万円以上の節税となることもあります。つまり、確定申告をするだけで、手元に戻ってくるお金が大きく増えるのです。
仮に、年収500万円の会社員が中古マンションを購入し、2,500万円のローンを組んだとします。初年度に確定申告を行い、住宅ローン控除を受ければ、所得税から約17.5万円が還付されます。これを使って家具を揃えたり、教育資金に回したりすることで、生活の質が大きく向上するでしょう。
住宅ローン控除を受けることは、単なる「税金の還付」ではなく、「お金のリターンを最大化する資産形成の第一歩」と言えます。確定申告を正しく行うことは、経済的なゆとりを持つために欠かせない重要な手段なのです。
中古マンション購入時に利用できる住宅ローン控除とは
中古マンションでも対象になる住宅ローン控除の基本
中古マンションでも一定の条件を満たせば、住宅ローン控除を適用して所得税や住民税の軽減を受けることが可能です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した人に対して、年末時点のローン残高の0.7%を最大10年間にわたって税額控除できる制度です。この制度は新築住宅だけでなく、中古住宅にも適用されます。ただし、中古物件の場合は「築年数」や「耐震基準」など追加の条件があります。これらを満たすことで、数十万円〜百万円単位の節税が可能になります。
例えば、2,500万円のローンを組んで中古マンションを購入し、初年度の年末残高が2,400万円だった場合、0.7%にあたる約16万8,000円がその年の所得税から控除されます。10年間で約168万円の節税が見込めるわけです。これは、家計に大きな余裕をもたらす金額と言えるでしょう。
中古マンションでも住宅ローン控除が使えることを知らずに申請しない人は少なくありません。結果として、せっかくの節税チャンスを逃してしまいます。購入前に制度の仕組みと条件を確認し、賢く利用することが家計管理の第一歩です。
適用条件と注意点を詳しく解説
住宅ローン控除は誰でも受けられるわけではなく、一定の条件をクリアしなければなりません。特に中古マンションの場合は、新築以上に条件が厳しくなる傾向があります。
主な適用条件は以下の通りです:
- 住宅の床面積が50㎡以上であること
- 自身が居住する目的で購入すること
- 借入期間が10年以上あること
- 合計所得が2,000万円以下であること
- 耐震基準を満たしていること(特に築25年以上の物件)
この中で特に注意が必要なのが「耐震基準」です。築25年を超える物件であっても、「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していれば控除対象となる場合があります。
築30年の中古マンションを購入したAさんは、当初「築年数が超えているから控除は無理だ」と思っていました。しかし、売主が耐震補強工事を実施しており、「耐震基準適合証明書」が発行されていたことで、住宅ローン控除の適用を受けることができました。このように、条件をよく確認することで控除の対象となるケースもあります。
適用条件を「どうせ無理だ」と決めつけるのは早計です。事前にしっかり調べ、必要な書類や制度を整えることで、たとえ築年数が経過した中古マンションでも十分に住宅ローン控除を受けるチャンスがあります。注意深く確認し、損をしないように行動しましょう。
この適用条件について詳細的に説明している記事をご用意しております。一度ご覧いただければと思います。
関連記事:中古マンションでローン控除を受けるための適用条件とは
中古マンション購入後の確定申告の流れとスケジュール
確定申告の提出時期と手順を把握しよう
中古マンションを購入した場合、住宅ローン控除を受けるためには、購入した翌年に「確定申告」を行う必要があり、提出時期と正しい手順を理解しておくことが大切です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、自動的には税金が軽減されるわけではなく、自ら税務署へ申告を行わなければなりません。特に購入1年目は、給与所得者(会社員)であっても例外ではなく、確定申告の手続きが必要になります。提出期間を逃すと、住宅ローン控除の初年度分が適用されず、大きな節税チャンスを失うことになります。
確定申告の提出期間は、原則として「翌年2月16日〜3月15日」まで。この期間を逃すと、その年の住宅ローン控除は原則適用されません。例えば、2024年に中古マンションを購入した場合は、2025年2月16日から3月15日までの間に申告を行う必要があります。この短い期間を逃さないためにも、早めの準備が重要です。
確定申告の提出時期は毎年ほぼ決まっているため、スケジュールをカレンダーに記載しておく、リマインダー設定をしておくなどして、確実に手続きを行いましょう。提出が遅れると取り返しがつかないため、「早め早めの行動」が鍵となります。
初めてでも安心なスムーズな申告の進め方
初めて確定申告を行う場合でも、手順を正しく理解し、事前に準備をしておけば、思っている以上にスムーズに進めることができます。
近年では、e-Tax(電子申告)やスマートフォンでの申告手続きが普及し、確定申告は以前よりもずっと簡便になっています。また、国税庁の「確定申告書作成コーナー」では、質問に答えていくだけで必要な書類が自動生成される仕組みが用意されているため、専門知識がなくても申告書が作れます。加えて、提出方法も「郵送」「税務署に持参」「オンライン(e-Tax)」から選択可能です。
例えば、会社員のBさんは、中古マンションを購入した翌年に初めての確定申告を行いました。e-TaxのIDとパスワードを取得し、マイナポータル連携を活用することで、源泉徴収票の内容も自動入力。必要書類をスキャンして添付し、所要時間はわずか1時間程度でした。「思ったより簡単だった」「もっと早くやればよかった」と話していたそうです。
「確定申告=難しい」という思い込みを捨て、最新のデジタルツールを活用することで、誰でも効率的に申告が可能です。特に住宅ローン控除の初年度申請は金額も大きく、面倒に感じてもやる価値は十分あります。正しい知識と準備を持てば、不安なく申告が完了するでしょう。
ホープスタイルでは、中古マンションの購入からリノベーションまで一気通貫で行うことができる会社です。
そのため、リフォーム/リノベーション会社では見ることのできない、中古マンション情報をHP上で多数ご覧できるようになっております。
ぜひ一度ホープスタイルのHPまでお越しいただき、自分たちに合った中古マンションをご覧ください。以下のリンクをクリックいただくと、ご覧いただけます。
中古マンションの確定申告に必要な書類一覧
抜け漏れを防ぐためのチェックリスト
住宅ローン控除を受けるために確定申告を行う際には、必要書類を漏れなく揃えることが大前提です。事前に準備すれば、提出時のミスや手戻りを防ぐことができます。
確定申告では「住宅ローン控除に関する内容を証明する書類」が数多く必要になります。これらが揃っていないと申告自体が受理されなかったり、税務署から再提出を求められる可能性もあります。また、どの書類が必要かをあらかじめ把握しておくことで、取得に時間がかかるものも余裕を持って準備できるというメリットがあります。
中古マンション購入時に必要な主な書類は以下の通りです:
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し(本人と家族の氏名・続柄の記載があるもの)
- 売買契約書または不動産売買の重要事項説明書の写し
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 金融機関が発行する「住宅ローン年末残高証明書」
- 勤務先から交付される「源泉徴収票」
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
これらを一つでも欠くと、住宅ローン控除が受けられない可能性があります。特に「年末残高証明書」や「登記事項証明書」は発行までに数日かかるため、早めの取得が肝心です。
確定申告で損をしないためには、早い段階で必要書類のチェックリストを作り、ひとつずつ確実に揃えていくことが重要です。提出ギリギリに慌てて準備するのではなく、1月中に完了を目指すと安心です。
書類の取得方法と注意点
各書類には取得先や方法が異なり、発行に時間がかかるケースもあるため、早めにスケジュールを立てて準備することが成功の鍵です。
確定申告に必要な書類は、1ヶ所でまとめて取得できるわけではなく、市役所、金融機関、法務局、勤務先など、さまざまな場所にまたがっています。平日にしか手続きできないケースも多く、タイミングを逃すと期限までに間に合わない恐れがあります。さらに、書類には有効期限や記載内容の正確性が求められるため、手続きに慎重さが必要です。
住民票は市区町村の役所で発行してもらいますが、「続柄の記載があるもの」「世帯全員のもの」など条件付きで求められることもあります。また、登記事項証明書は法務局で取得し、物件の住所が正確であることが記載されているかをチェックする必要があります。年末残高証明書はローンを借りた金融機関から送付されますが、紛失してしまった場合は再発行の手続きが必要です。再発行には1〜2週間かかる場合もあるため、紛失には注意が必要です。
「どこで何を入手すればよいか」を明確に把握し、休日に動けない施設については事前に開庁時間を調べておくなど、計画的に進めましょう。申告の締切直前に慌てて動くと、取得が間に合わないリスクもあるため、1月中旬からの行動がベストです。
住宅ローン控除の適用条件を詳しく確認しよう
節税のためのポイントを押さえる
住宅ローン控除を確実に受けるためには、事前に「適用条件」を正しく理解し、自身の状況が条件を満たしているかをチェックすることが重要です。
住宅ローン控除は非常にお得な制度ですが、「誰でも無条件で受けられるわけではない」という点をまず理解する必要があります。控除の適用には細かな条件が定められており、それらを一つでも満たしていないと、控除が適用されない場合があります。条件を知らずに申告し、後から不備を指摘されると、修正申告や控除の適用除外といったリスクに発展する可能性があります。
住宅ローン控除の主な条件には、以下のようなものがあります:
- 購入した住宅が自分の「居住用」であること(投資用・賃貸用は対象外)
- 床面積が50㎡以上であること(壁芯面積ではなく内法面積で判断)
- 借入期間が10年以上あること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 建築確認日が一定の耐震基準を満たしていること(特に中古の場合)
- 確定申告を初年度に行っていること(初年度申告がないと2年目以降も受けられない)
これらのうち一つでも条件を欠くと、控除は適用されません。特に注意したいのが「耐震性」の証明です。築25年以上の物件は、そのままだと原則控除対象外になりますが、「耐震基準適合証明書」を取得していれば適用されるケースもあります。
「控除が使えるかどうか」は、購入後ではなく、購入前に確認しておくべき事項です。不動産会社や住宅ローン担当者に任せきりにせず、自分で条件をひとつひとつ確認し、確実に控除を受けられるよう事前準備を怠らないことが、将来の節税につながります。
見落としやすい条件や落とし穴に注意
住宅ローン控除の条件には、見落としがちなポイントや誤解されやすい要件が多くあります。特に中古マンションの場合、特別な注意が必要です。
制度そのものはシンプルに見えても、実際には購入物件の築年数、床面積の表記方法、登記上の居住時期、家族との共有状況など、細かい条件が控除の可否を左右します。見た目や説明だけで判断せず、資料をもとに慎重に確認しなければ、最終的に控除対象外となってしまう可能性があります。
例えば、「床面積が50㎡以上」と聞いて安心していたものの、実際には「壁芯面積」が50㎡であり、「内法面積」が49㎡だったため、住宅ローン控除の適用を受けられなかったケースもあります。
また、「入居は引っ越し後すぐの予定」としていたが、実際の登記上の居住日は3ヶ月後になり、その年の控除が適用されなかった事例も存在します。さらに、「耐震診断をしていた」と思っていたが、「証明書の取得をしていなかった」ため、控除が否認されたという事例もあります。
これらのような見落としやすいポイントを一つひとつ確認し、書類として証明できる状態を整えることが、住宅ローン控除の成功につながります。購入時には、「控除を受ける前提」で準備を進めることが何より重要です。
共有名義・連帯債務で中古マンションを購入した場合の申告対応

夫婦共有名義のときに注意すること
中古マンションを夫婦で共有名義にした場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能ですが、正確な「持ち分割合」と「ローン返済実績」に基づいて申告を行う必要があります。
住宅ローン控除は「住宅ローンを返済している本人」が対象です。したがって、共有名義の場合は登記上の持ち分だけでなく、実際にどのくらい返済しているか、ローンの負担割合に応じて申告を分ける必要があります。税務署では「収入状況」「口座引き落とし記録」「契約内容」などを精査し、不自然な申告があれば指摘される可能性もあります。
たとえば、3,000万円の中古マンションを夫婦で50%ずつ共有名義とし、2,500万円のローンを同様に50%ずつ負担した場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。ただし、ローンの返済がどちらか一方の口座から行われている場合、その人しか控除を受けられない可能性もあるため、口座の分け方や記録の残し方が重要になります。
共有名義で住宅ローン控除を受けるなら、「登記上の持ち分」「返済実績」「申告額の按分」に注意し、夫婦それぞれが適正な控除を受けられるよう書類を整えておくことが大切です。
連帯債務での控除申請はどうなる?
連帯債務でローンを組んだ場合は、各自が負担しているローン残高に応じて、それぞれ住宅ローン控除を申告できます。ただし、控除の分け方には明確なルールがあるため、事前の確認が必須です。
連帯債務とは、夫婦や親子など複数の人が連名でローンを組み、全員が全額の返済責任を負う契約形態です。しかし、実際の返済が各人で按分されている場合には、それぞれが控除を申告できます。ただし、金融機関から送られてくる「年末残高証明書」は1枚のみであり、申告の際にはその証明書をもとに「按分割合」を記載して申告する必要があります。
Aさん夫婦は連帯債務で3,000万円の住宅ローンを契約し、実際の返済も半々で行っていました。年末残高が2,800万円だったため、それぞれが1,400万円を申告対象額として住宅ローン控除を受けることができました。なお、確定申告書にはそれぞれが「連帯債務である旨」と「負担割合の証明(支払記録など)」を添付し、問題なく控除が認められました。
連帯債務の場合も、正しく対応すれば双方が控除を受けられる可能性が高くなります。ただし、年末残高の「按分」とその根拠を示す資料は必須です。曖昧なまま申告せず、しっかりと事前準備を整えて確定申告に臨みましょう。
リフォーム込みで購入した中古マンションの申告方法
リフォーム費用が控除対象になる条件
リフォーム費用も一定条件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。ただし、すべてのリフォームが対象になるわけではなく、「特定の目的に該当する工事」である必要があります。
住宅ローン控除が適用されるのは、「居住用住宅」に関する借入金のうち、増改築・リフォームを行った工事が「一定の要件を満たす場合」に限られます。たとえば、バリアフリー化、省エネ対策、耐震補強などが該当します。また、ローン契約の目的にも「増改築資金」と明記されている必要があり、資金使途があいまいな場合は対象外となるケースもあります。
築30年の中古マンションを購入したCさんは、購入後に耐震改修と断熱窓の設置を含むリフォームを実施。ローン契約書にもリフォーム目的が記載されており、施工会社からの証明書も取得済みでした。結果として、住宅ローン控除の対象として認められ、減税効果を得られました。一方、インテリアや壁紙の変更など、資産価値を高めない単なる模様替えは対象外となるため注意が必要です。
リフォームが控除の対象になるかどうかは、「工事の内容」「資金の使途」「必要書類」の3点で判断されます。購入と同時にリフォームを計画している場合は、事前に適用条件を確認し、証明書類をそろえておくことが成功のカギとなります。
リフォーム工事とはどんなものがあるのか?以下に参考記事を掲載しておきます。
関連記事:
内装リフォームを成功させるための費用相場と施工の流れや注意点まで徹底解説
和室から洋室にリフォームするなら絶対に押さえたい費用と施工のポイントとは
水回りリフォームの費用を徹底解説!相場や節約術までわかりやすく紹介
書類の分け方と提出時のポイント
中古マンションの購入とリフォームを同時に行った場合、住宅ローン控除の申告では「購入費」と「リフォーム費」を明確に区別した書類の提出が求められます。
税務署は、「購入資金」と「増改築資金」の使い道が明確であることを求めてきます。両者の金額が混在していたり、支払いの証拠が不明確な場合、控除が認められない可能性があります。したがって、リフォーム部分については、工事契約書、請求書、支払い証明書(領収書や振込明細など)を明確に分けておくことが重要です。
Dさんは、マンション本体に2,500万円、リフォーム費用に500万円をかけ、合計3,000万円のローンを組みました。住宅ローン控除を受ける際、購入部分とリフォーム部分の契約書をそれぞれ分けて税務署に提出。さらに、施工会社から「工事内容がバリアフリー・省エネに該当する旨の証明書」を取得したことで、両方の費用が控除対象として認められました。
申告書には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」とともに、リフォームに関する契約書・証明書を添付することが必要です。「ひとつのローンだから大丈夫」と油断せず、支出内容を明確に分けておくことが、スムーズな申告と控除適用につながります。
中古マンション購入後に一時的に居住しない期間があった場合
控除の適用に影響はある?実際の扱いを解説
中古マンション購入後にすぐに住めない事情があった場合でも、住宅ローン控除の対象になるケースがありますが、「いつから居住したか」が明確であることが条件となります。
住宅ローン控除を受けるには「居住の用に供した年」であることが前提です。つまり、購入しても実際に住み始めていなければ、その年の控除は原則として受けられません。ただし、事情によっては「やむを得ない未居住」として認められる場合もあります。ここでポイントとなるのが、税務署へ「居住予定日」「未居住理由」などを明確に説明できるかどうかです。
Eさんは2024年10月に中古マンションを購入しましたが、転職が重なって引っ越しが翌年の1月になってしまいました。そのため、2024年中に居住を開始できなかったことになります。この場合、住宅ローン控除は2024年分ではなく、実際に入居した2025年から適用されます。逆に、12月25日など年末ギリギリに入居し、住民票を移していれば、その年の控除対象になる可能性が高いです。
居住開始時期は、「いつ住んだか」が記録として残る重要な要素です。住民票の移動日やライフラインの契約開始日、引っ越し業者の利用日など、居住の証拠をきちんと残しておくことが、控除を受けるうえでのカギになります。
転勤や事情による未居住期間の対応方法
転勤や家庭の事情で一時的に住めなかった場合でも、条件を満たせば住宅ローン控除が認められることがあります。重要なのは「居住の意思」と「居住予定の具体性」です。
税法では、購入してすぐに住めない場合でも、「合理的理由がある」と認められれば、控除対象となることがあります。たとえば、購入後に転勤が決まり一時的に家族で住めなかった場合などが該当します。この際には、「いずれ戻って住む意思がある」「単身赴任で家族が住んでいる」「一時的な事情での未入居」といった点を説明し、書類や住民票、勤務先の辞令などで裏付ける必要があります。
Fさんは2023年に中古マンションを購入したものの、入居直前に急な海外転勤が決定。家族も同行したため空き家状態が続きました。しかし、2025年に帰任し入居を開始。購入時から「いずれ自宅として使う」という明確な意思があり、勤務先の転勤命令書などをもとに税務署に相談した結果、住宅ローン控除の適用を受けることができました。
このように、「住む意思」が証明できれば、未居住でも柔軟に判断されるケースがあります。
未居住の事情がある場合は、曖昧にせず税務署に事前相談するのが賢明です。居住実績が遅れた場合でも、必要な書類を提出し、居住の意思と理由が合理的であれば、住宅ローン控除のチャンスは残されているのです。
確定申告を忘れてしまった場合の対処法
過去分の申告でも控除は受けられる?
住宅ローン控除の申請を忘れてしまっても、5年以内であれば「還付申告」という形で過去分を取り戻すことができます。
確定申告には申告期限がありますが、「払いすぎた税金の還付」を求める申告(=還付申告)は、5年間さかのぼって行うことが認められています。つまり、初年度の確定申告を忘れてしまっても、その後5年以内であれば、必要書類をそろえて還付申告を行うことで住宅ローン控除を適用させることが可能なのです。
Gさんは2020年に中古マンションを購入し住宅ローンを組んだものの、申告の必要性を知らずに2021年・2022年もスルー。しかし、2023年に控除制度の存在を知り、税務署に相談。結果、2020年分の確定申告を還付申告として提出し、無事にその年の住宅ローン控除を受けることができました。なお、2021年・2022年分についても、同様に順次申告を行い、控除が認められました。
申告を忘れたからといって諦める必要はありません。5年以内であれば住宅ローン控除の恩恵はまだ受けられます。思い出したその時が行動のチャンスです。
必要な手続きと期限
還付申告を行うには、通常の確定申告とほぼ同じ書類と手順が必要であり、5年以内に税務署に提出することで還付を受けることが可能です。
還付申告と通常の確定申告の違いは、申告の目的が「税金の還付」である点です。手続き上は同じように書類を用意し、計算明細書を記入し、確定申告書を作成して税務署に提出します。ただし、還付申告は「過去分」の申告となるため、提出期限が購入年から5年以内であることが必須となります。また、必要書類もその当時のものを用意する必要があり、再発行が必要なケースも多いので、早めの行動が求められます。
Hさんは、2019年にマンションを購入したにもかかわらず、2020年の申告を失念。2024年に「あと少しで5年が経つ」と気付き、慌てて年末残高証明書、当時の源泉徴収票、住民票、売買契約書、登記事項証明書などを揃えて税務署に提出しました。ぎりぎりでしたが、5年の期限内だったため、無事に還付を受けられました。
確定申告を忘れてしまっても、住宅ローン控除は取り戻せます。ただし、5年という期限は絶対です。「今さら無理かも」と思わずに、まずは税務署に相談し、早急に手続きを進めることが大切です。
中古マンション購入後の確定申告を正しく行うために
中古マンション購入後の確定申告で損をしないためのまとめ
中古マンション購入後に住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を正しく、期限内に行うことが最も重要です。申告の内容や手続きにミスがあると、節税の恩恵を受けられなくなってしまうため注意が必要です。
中古マンションを購入した際の住宅ローン控除は、初年度に確定申告を行わなければその後の適用も受けられなくなるという非常にシビアな制度です。さらに、申告内容に誤りがあった場合、税務署からの修正依頼や最悪の場合控除の否認を受けるリスクもあります。そのため、書類の準備・記載内容の確認・提出期限の厳守は絶対条件と言えるでしょう。
Iさんは、中古マンション購入後に確定申告の準備をしていましたが、住民票の住所が旧住所のままで提出してしまい、住宅ローン控除の適用が一時保留されました。税務署に指摘を受けて住民票を修正し再提出することで控除が認められましたが、もしそのままにしていたら還付金は受け取れなかったでしょう。このように「ちょっとした確認ミス」が大きな損失につながるのです。
確定申告は「やればよい」ではなく、「正確に、期日までに、適切にやる」ことが求められます。特に住宅ローン控除の申告は提出書類も多く、初年度は複雑になりがちです。「自分でできるか不安」という人は、税務署に相談する、税理士に一度見てもらうなど、専門家の力を借りることも検討しましょう。申告を正しく行うことが、賢い節税と安心の住まいづくりにつながります。
ホープスタイルにお問い合わせや、ご相談をご希望の方は、以下からご連絡ください。
無料で現在のご状況を伺い、最適な中古マンションやリノベーションプランをご提案させていただきます。

