
中古マンションの購入は、人生の中でも大きな買い物のひとつです。しかし「物件価格」ばかりに注目してしまいがちで、実際には「諸費用」と呼ばれるさまざまな追加費用が発生することを見落としがちです。
こうした諸費用の内容を事前にしっかり把握しておくことで、予算オーバーを防ぎ、計画的な資金準備が可能になります。
本記事では「中古マンション購入諸費用の全体像と節約術を初心者にもわかりやすく解説」というタイトルのもと、中古マンション購入時にかかる諸費用の内訳や、費用を抑える方法、資金調達の工夫について詳しくご紹介します。
これから物件購入を考えている方、具体的な費用感を知りたい方にとって役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
中古マンションの購入に関しての記事は、こちらです。
関連記事:
中古マンションを購入する流れとは。住宅ローン・現金で買う場合、購入と同時にリフォームする場合の流れや必要な期間を解説
中古マンション購入の注意点知っておくべきポイントは?チェックポイントもご紹介
中古マンションを購入するにあたり、ご不安は多いのではないのでしょうか。
ホープスタイルLINE公式のお友達追加で、お手軽に中古マンションの購入やリノベーション準備の方法を「無料特典」として、受け取ってもらえます。
少しでも気になる方は、以下の画像をクリックしていただき、お友達追加をお願いします。
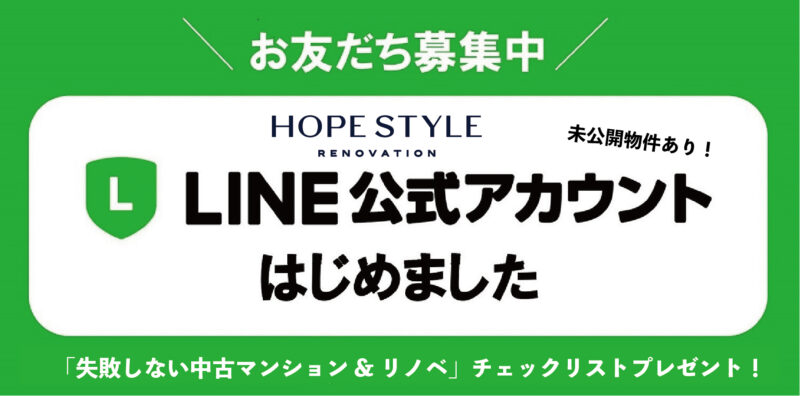
目次
中古マンション購入に必要な諸費用とは?その全体像と基本を押さえよう
物件価格以外にもかかる中古マンション購入諸費用の種類
マンション購入時には「物件価格」が大きな関心事となりがちですが、実際には「諸費用」という追加費用が大きな割合を占めることを見逃してはいけません。諸費用を正しく理解することは、購入予算を正確に立て、資金不足を防ぐうえで非常に重要です。
諸費用とは、不動産の売買契約や登記、ローンの借入、税金、保険など、物件の引き渡しを受けるまでに必要なさまざまな支出の総称です。一般的には物件価格の約6~10%が目安とされています。仮に3,000万円の中古マンションを購入するなら、180万円〜300万円の諸費用がかかることになります。
例えば、不動産会社に支払う「仲介手数料」は、通常「物件価格 × 3% + 6万円(+消費税)」という計算式で算出され、100万円近くになるケースもあります。
また、契約書に貼る「印紙税」や、住宅ローン関連の「事務手数料」「保証料」「団体信用生命保険料」なども発生します。さらには「火災保険料」や「地震保険料」、そして「登記費用」「登録免許税」「不動産取得税」など、聞き慣れない名前の費用が次々にかかってきます。
このように、中古マンション購入時には多種多様な諸費用が発生します。物件価格のほかに、どのような支出があるのかを事前に洗い出し、資金に余裕を持たせておくことが、後悔しない不動産購入の第一歩と言えるでしょう。
新築とどう違う?中古マンション購入諸費用の目安
中古マンションと新築マンションでは、かかる諸費用の内訳と金額が異なります。特に中古物件の場合は「仲介手数料」が発生することが大きな違いであり、この点が費用全体に与える影響は見過ごせません。
一般的に、新築マンションはデベロッパー(売主)から直接購入することが多いため、仲介手数料がかからないことが多いのですが、中古マンションは不動産会社が売主と買主を仲介する形になるため、その手数料が発生します。この差だけでも数十万円〜100万円前後の違いが生じます。
また、新築マンションではあらかじめ保険や保証などがパッケージ化されている場合も多く、費用が明確である一方で、中古物件では火災保険や地震保険を自分で選定・加入しなければならないため、個別のコスト計算が必要になります。
さらに、物件の築年数や状態によっては、購入後すぐに修繕やリフォームが必要になるケースも少なくありません。これもまた「想定外の諸費用」として予算に加えておくべき項目です。
新築と中古では諸費用の内容が異なり、特に中古マンションでは予測しにくい費用が発生しやすいため、事前の調査と資金計画が重要です。特に仲介手数料やリフォーム費用の有無によって、大きく総支払額が変わることを理解しておく必要があります。
中古マンション購入諸費用の詳細とそれぞれの役割
契約時に発生する中古マンション購入諸費用の内訳
中古マンションを購入する際、最初に発生する諸費用が「契約時費用」です。これは、購入の意思表示と取引を成立させるために必要なものであり、購入プロセスの初期段階での重要な資金負担となります。
まず代表的なのが「手付金」です。これは買主が契約締結時に売主へ支払う金額で、一般的に物件価格の5〜10%が相場とされています。例えば3,000万円の物件であれば、150万〜300万円程度の手付金を現金で用意しなければなりません。手付金は契約解除の際の違約金ともなるため、非常に重要な意味を持っています。
次に「印紙税」です。これは売買契約書に貼付する印紙代で、契約金額に応じて課税されます。3,000万円程度の物件なら印紙税は1万円ですが、これも事前に準備しておく必要があります。
契約時に発生する諸費用は、単なる「最初のお金」ではなく、取引の信頼性と正式性を裏付けるためのものです。金額は少なく見えても、全体としては数十万円〜数百万円の現金が必要になるため、あらかじめ資金準備とスケジュールを明確にしておくことが大切です。
ローン関連で必要な中古マンション購入諸費用の項目
住宅ローンを組んで中古マンションを購入する場合、ローン契約に関連する諸費用も大きな負担の一部となります。これらは「融資実行のための手続き費用」として発生し、金融機関によって金額や項目が異なります。
代表的な費用のひとつが「融資事務手数料」です。これは、ローンを手配するために銀行が請求する手数料で、定額型(3万〜5万円程度)と定率型(借入額の2.2%など)があり、定率型は数十万円になることもあります。
また、「保証料」も見逃せません。これは、借入者が返済できなくなった場合に備えて保証会社に支払うもので、借入額の1~2%が相場です。最近では「保証料無料」を掲げる金融機関もありますが、その場合は金利がやや高めに設定されていることが多く、トータルコストで比較することが重要です。
さらに「団体信用生命保険料」もあります。これは、借入者が死亡・高度障害となった場合に、ローンの残債が保険で完済される仕組みです。多くの金融機関では金利に含まれているケースが多いものの、ガン保障などを追加する場合は別途費用がかかります。
ローン関連費用は金額的にも大きく、借入額や金融機関によって大きく変動します。契約前に複数の金融機関のプランを比較し、自分にとって最適な条件を選ぶことが、長期的な返済負担を軽減するカギとなります。
登記・登録関連の中古マンション購入諸費用
不動産を取得した際には、その権利を法律的に証明するための「登記」が必要です。この登記にも複数の費用が発生し、それぞれが購入手続きの中で欠かせない役割を果たします。
まず、「所有権移転登記」があります。これは、売主から買主へ名義を移すための登記で、法務局へ申請する必要があります。登記には「登録免許税」が課され、これは固定資産評価額に一定の税率(一般的には2%)をかけて算出されます。評価額と税率によって異なるため、事前に確認が必要です。
次に、「抵当権設定登記」です。住宅ローンを利用する場合は、金融機関が担保としてその不動産に抵当権を設定します。この登記にも登録免許税がかかり、借入額の0.4%が一般的です。
また、登記申請は通常、司法書士に依頼するため、その報酬も発生します。相場としては5万〜10万円程度で、複数登記がある場合はさらに高額になります。
登記関連費用は専門性が高く、金額も大きいため、事前に見積もりをとっておくことが重要です。また、登記手続きを自分で行うことで司法書士報酬を節約する選択肢もありますが、正確性と法的知識が求められるため慎重に検討しましょう。
税金とその計算方法:中古マンション購入時の要注意ポイント
不動産を購入すると、さまざまな税金も発生します。これらは「取得時」と「保有中」そして「将来的な売却時」に分類されますが、今回は特に購入時に関わる税金にフォーカスします。
まず「不動産取得税」があります。これは、物件の購入後に一度だけ課税される地方税で、固定資産評価額の3%(軽減措置あり)が基本です。新築に比べ中古物件は評価額が低くなる傾向があるため、やや負担は軽くなる場合がありますが、地域によって制度が異なるため注意が必要です。
次に、「固定資産税」と「都市計画税」です。これらは毎年1月1日時点での所有者に課される税金で、購入時期によっては、売主と日割りで精算することもあります。年間の納税額は物件の立地や広さにより異なり、年10万円以上かかることも珍しくありません。
また、「印紙税」も前述のとおり契約時に必要な税金です。加えて、購入後のリフォームに対しては消費税が発生する点も見落とせません。
税金は一見すると少額に見えるものの、積み重ねると大きな出費になります。しかも、支払いタイミングがバラバラであるため、資金繰りに混乱を生じさせることも。各種税金の内容と支払いスケジュールを正しく把握し、計画的な資金準備を進めることが求められます。
具体的な数字で見る中古マンション購入諸費用シミュレーション
3000万円の中古マンションを購入した際の諸費用例
中古マンションを購入する際、最も現実的な目安となるのが「価格別の諸費用シミュレーション」です。ここでは特に多くの人が検討する価格帯である「3,000万円」の中古物件を例にとって、実際にどのような諸費用がかかるのかを具体的に見ていきましょう。
物件価格3,000万円の中古マンションでは、諸費用として約180万円〜300万円程度が必要になるケースが一般的です。
【根拠】
この金額は、「仲介手数料」「住宅ローン関連費用」「登記費用」「税金」「保険」など、複数の費用を合計したものです。以下は主な費用の内訳です。
- 仲介手数料:約105万円(3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税)
- 住宅ローン事務手数料:約3万~66万円(定額型または定率型)
- 保証料:約60万円(借入額の2%と仮定)
- 登録免許税・司法書士報酬:約20万円
- 火災保険料:約10万円(10年間)
- 印紙税:1万円(契約書に貼付)
- 固定資産税・都市計画税の精算金:3〜5万円
これらを合計すると、最低でも180万円程度、場合によっては300万円を超えることも珍しくありません。
たとえば住宅ローンに定率型の事務手数料(借入額の2.2%)を選んだ場合、3,000万円の借入で手数料だけで66万円になります。ここに保証料や保険料、登記費用などを加算していくと、200万円台半ばになるのが現実的です。
3,000万円の中古マンションを購入する場合、単に「物件価格が払えるかどうか」ではなく、「+10%分の諸費用を支払える余裕があるか」を見極めることが重要です。ローン審査においても諸費用分を現金でまかなえるかは大きな審査項目です。計画的に資金を確保し、安心して取引に臨みましょう。
ケース別で考える中古マンション購入諸費用の幅
中古マンションの購入にかかる諸費用は、一定ではありません。物件の条件や選ぶ金融機関、オプションの有無によって大きく変動します。そのため、シミュレーションは「一例」ではあっても、「最終的な正解」にはなりません。
購入条件や選択肢によって、諸費用の総額は100万円台から300万円超まで大きな差が生じます。
たとえば、仲介手数料が無料の物件を選べば約100万円近い節約が可能ですし、保証料が無料の住宅ローンを選べば、それだけでさらに数十万円の差が出ます。
さらに、登記を自分で行えば司法書士報酬も浮かせることができます。
中古マンション購入の諸費用は、選択次第で大きく変わります。物件の価格だけでなく、「どこでお金を使い、どこで抑えるか」という視点が、費用を最適化するカギとなります。シミュレーションを1パターンだけで終わらせず、複数ケースを比較する習慣をつけましょう。
ホープスタイルは、皆様のご予算に合わせた「物件」と「リノベーションプラン」をご提案しています。
その際に必要になるのが、予算のシミュレーションです。
おおよその予算シミュレーションをしておくだけでも、イメージの湧き方が違いますので、ぜひ以下のリンクからお試しください。
中古マンション購入諸費用を抑えるためにできること

仲介手数料を交渉して中古マンション購入諸費用を下げる方法
中古マンションを購入する際、最もインパクトのある費用のひとつが「仲介手数料」です。しかしこの費用、実は“交渉次第”で大幅に節約できる可能性があります。
仲介手数料は交渉によって減額、もしくは無料になることがあるため、節約できる有力なポイントのひとつです。
宅建業法では「仲介手数料の上限」は定められているものの、「下限」は明記されていません。そのため、不動産会社の裁量で割引や無料対応が可能です。特に売主からすでに報酬を得ているケースでは、買主からの仲介手数料を減額できる余地があります。
たとえば3,000万円の中古マンションを購入する場合、仲介手数料は「約105万円(税込)」が上限です。これを半額に交渉できれば、50万円以上の節約に。さらに「売主物件(=不動産会社が売主)」の場合は、そもそも仲介手数料が不要なことも。事前に物件情報をよく確認することで、大きな差を生むことができます。
仲介手数料は「言われるがままに支払う」ものではありません。交渉次第で大きな節約になるため、遠慮せずに相談してみましょう。また、仲介手数料無料をうたう不動産会社の活用も有効な選択肢です。
保険や登記は自分で選ぶ!中古マンション購入諸費用の節約テク
中古マンション購入にかかる保険料や登記費用も、実は「選び方」で大きく変わってきます。特に火災保険や司法書士報酬は、不動産会社の「お任せ」で進めてしまう人が多いため、見直しの余地が大きい費用項目です。
保険や登記手続きは自分で選んだり手配したりすることで、数万円から十数万円の節約につながります。
火災保険は、補償内容・補償期間・免責金額などを比較することで、無駄な支出を減らすことが可能です。不動産会社が紹介する保険プランは割高なケースもあり、自分でインターネットなどを活用して見積もりを取り、条件の良いプランを選べば費用を抑えられます。
登記についても、司法書士へ依頼せず「自分で登記」することで、報酬分(5万円~10万円)を削減することができます。ただし、専門的な知識や時間が必要になるため、リスクと手間を十分に理解した上で行う必要があります。
Aさんはネット型の火災保険に加入し、10年間の保険料を8万円で済ませました。一方で不動産会社から勧められた保険では13万円だったため、5万円の節約に成功。また、登記手続きを自力で行い、約7万円の司法書士報酬も節約しました。
「お任せにしない」姿勢が、諸費用節約の第一歩です。保険も登記も、自分で調べ、比較し、納得した選択をすることで、確実に支出を抑えることができます。
保証料無料の住宅ローンで中古マンション購入諸費用を削減
住宅ローンの「保証料」は数十万円にも上る高額な費用ですが、最近ではこの費用をカットできるローンプランも増えてきました。保証料を無料にするだけでも、総額に大きなインパクトを与えることができます。
保証料無料の住宅ローンを選ぶことで、諸費用の中でも特に高額な「保証料」を節約できます。
保証料は、ローンの返済が滞った場合に備えて保証会社へ支払うもので、借入額の1〜2%が目安です。たとえば3,000万円のローンでは30万〜60万円にもなります。一部のネット銀行や地方銀行では、この保証料が無料になるプランを用意しており、トータルコストで非常に有利です。
ただし注意点として、保証料が無料な代わりに金利が高めに設定されている場合や、融資条件が厳しくなっている場合があります。そのため「金利と保証料の合計負担」を試算して比較する必要があります。
Bさんはメガバンクのローンで保証料を支払い、40万円の諸費用がかかりました。一方Cさんは、ネット銀行の保証料無料プランを選び、ローン契約費用を大きく削減。金利はやや高かったものの、10年で見れば支払い総額はCさんの方が少なく済みました。
保証料無料ローンは、賢く使えば大きな味方になります。目先の金利だけでなく、保証料込みでの総費用を比較して、よりお得なプランを見つけることが節約への近道です。
諸費用ローンって?中古マンション購入諸費用に使える資金調達法
頭金や自己資金が少ない人におすすめの中古マンション購入諸費用の対処法
中古マンションの購入を検討しているものの、「物件価格は用意できるが、諸費用分の現金が足りない」という人は少なくありません。こうしたケースで注目されているのが「諸費用ローン」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、しっかりと仕組みを理解すれば、非常に心強い資金調達手段となります。
諸費用ローンは、頭金や貯金に不安がある人にとって、中古マンション購入を現実のものにするための有効な選択肢です。
中古マンションの購入では、仲介手数料・登記費用・住宅ローン関連手数料・保険料・税金など、物件価格とは別に数十万〜数百万円単位の諸費用がかかります。諸費用は住宅ローンに含めることができないケースもあるため、現金での支払いが求められる場合も。その際に役立つのが、諸費用専用のローンです。
このローンは、多くの場合、住宅ローンとは別枠で設定され、比較的短期間(5年以内)かつ金利はやや高め(年3〜5%程度)に設定される傾向があります。そのため、毎月の返済額はやや上がりますが、一時的な資金不足を補うには最適です。
たとえば、3,000万円の中古マンション購入に対し、諸費用が約200万円必要な場合。自己資金が150万円しか準備できていない方が、残りの50万円を諸費用ローンで補うとします。5年間・金利4%で借入れた場合、月々の返済額は約9,200円となり、現実的な負担で補填が可能です。これにより、計画通りに購入を進めることができます。
諸費用ローンは、自己資金不足というハードルを越えるための有力な解決策です。ただし、通常の住宅ローンに比べて金利が高く、審査も別で行われるため、利用前に複数の金融機関の条件を比較することが大切です。計画的な利用で、賢く中古マンション購入を実現しましょう。
まとめ:中古マンション購入諸費用の全体像と節約のポイントを再確認しよう
中古マンションの購入を検討する際、「物件価格」にばかり注目していませんか? 実は、その裏側にはさまざまな「諸費用」が存在しており、これらを見落としてしまうと、資金計画が崩れたり、思わぬ支出に苦しんだりするリスクがあります。
中古マンション購入における「諸費用」の正確な把握と、可能な限りの節約が、安心で後悔のない不動産取引につながります。
物件本体とは別に、仲介手数料・登記費用・住宅ローン関連費用・税金・火災保険料など、さまざまな名目の費用が発生します。合計すると物件価格の6〜10%に達することも珍しくありません。これを無視して予算を組めば、思わぬ不足に直面する可能性もあります。
たとえば、3,000万円の中古マンションを購入する場合、最大で300万円近い諸費用が必要です。これに気づかず予算を3,000万円ちょうどに設定していたとしたら、購入そのものが成立しない事態になりかねません。しかし、仲介手数料の交渉や保険の見直し、保証料無料の住宅ローン活用など、工夫次第で数十万円の節約が可能になります。
中古マンションの購入では、「価格+諸費用」という視点を持つことが非常に重要です。そして、節約できる部分は積極的に見直し、賢く予算を最適化する姿勢を持ちましょう。本記事を通して得た知識が、あなたの住まい選びをより安心・安全なものにすることを願っています。
現在中古マンションを購入して、リノベーションして住まわれるご家庭が増えております。弊社は中古マンションリノベーションを専門とする会社ですので、大阪市内にある物件情報を多数取り揃えております。
ホープスタイルにお問い合わせや、ご相談をご希望の方は、以下からご連絡ください。
無料で現在のご状況を伺い、最適な中古マンションやリノベーションプランをご提案させていただきます。

